

2023/5/5, Fri.
- ここさいきんはまったく文を書かず、本もたいして読まず、読み書きからはなれていた。やはり左手首が文字通りネックで、打鍵をすると体調に良くないので。Notionのまいにちの記事すら五月にはいってからはつくっていなかったくらいだ。日記の読みかえしなんかもしばらくしていない。
- 四月終盤からの日々を要約しておくと、一七日の月曜日に出勤途中の電車で途中下車してしまい、それからしばらくは体調がだいぶよろしくなく、左半身がしびれたりしていたのだが、四月いっぱい勤務は休みにしてもらってひたすらだらだらしているあいだにまあたしょうはよくなってきた。しかし二五日の火曜日に薬がもうとぼしいからと医者に行こうとしたところが、(……)駅までは行ったのだけれど午後五時の駅や電車にひとはおおく、ホームで待っているあいだからそろそろ電車が来るとなると緊張がたかまったし、入線してきたのをみても動悸にやられて苦しいので乗れないことは明白、そこでその日は引き返して帰り、母親に電話をかけて、わるいがちかいうち車で来てもらって医者まで連れて行ってくれないかとたのんだ。それで二七日の午前に父親に来てもらって医者に行ってヤクを確保、その後実家にも寄ってから夕刻、こんどは母親に(……)駅付近まで送ってもらい、二九日にはまたおなじところで待ち合わせをして車で実家へ、翌三〇日には兄夫婦と子どもが来て、それからきのうまでは姪と甥の世話なり地元の祭りの手伝いなりで忙殺されていた。
- 四月中はやる気が出ずマジでだらだらしまくっていたので本も読まず文も書けないとなるとやっぱりわりと生きる甲斐がないなあという感じだった。実家に行ってからはやることがたくさんあったのでそれにまぎれて生の甲斐がないとはおもわなかったが。子どもの世話はひじょうにたいへんだし祭りの役目のほうでもくたくたになって、ここ数日はひとりの時間というものがとぼしかったから、対人接触のキャパシティがかなり消耗させられた感があった。まえにも書いたが他者などとおおげさにいうまでもない、他人とは端的に疲労だ。それにしても子どもというのはこちらのおもいどおりにならない存在のさいたるもので、それをある程度コントロール可能な存在に変成させていくのが養育であり教育なのだろうけれど、よほどの忍耐力と献身の姿勢がなければかれらにつきあうことはできない。じぶんは親になるのは無理だなとあらためておもった。つねに他人とともにいなければならないというのが耐えられない。三日の夜に(……)さんとはなしたときに、まえに子孫を残す気はないって言ってたけど、と言われて、そんなこと言ってましたかと笑ったが、むべなるかなというところだ(まあ、「子どもを持つ気がない」と「子孫を残す気がない」だとその意味するところはたしょう違ってくるが)。
- そういうわけで読み書きにやる気が出なかったり忙しかったりする近頃で、そろそろおれも駄目かな、じぶんの生の意義をうしなうかなとおもったが、いちおうきょうからまたはじめようかと。といっていまこうして打鍵していてもやはりからだにはまずいので、書くなら手書きでやるしかない。いぜんも記したとおり手帳だとちいさくて書きづらいのでもうノートに日記をつけるむかしながらの方式にして、ブログへの投稿はめんどうくさいのでやめようかと。写真を撮ってドライブにあげ、パソコンで落としてNotionに貼ることすらめんどうくさい。とにかく左手がネックなので、それをつかう活動(つまり打鍵とギターだが)はせず、まあ一年か三年か今後一生かわからないが文を書くならアナログで。書き抜きもやはり手書きでやろう。ただネット記事を読んでコピペするのは問題ないから、生存報告がてらそれくらいはブログに投稿しても良いかもしれない。余裕があれば一言日記を足すとか。この人工知能時代に時代錯誤きわまりないが、からだがそういう状態になってしまったのだからしかたがない。強いられた条件を武器へと変えるのが人間の叡智というものだ。アナログでやっているうちに打鍵しても問題ないからだにもどればまたキーボードで書くようにすればよいし、変わらなければそれまで。ともあれいちおうまだ読み書き、読むだけでなく書くほうもつづける気はあるらしい。ひとはじぶんの欲望によって書く、そしてわたしはまだ欲望し終えていないのだ、というわけだけれど、じぶんがほんとうに欲望し終えていないのかどうか、果たしてじぶんじしんで明確にわかるものだろうか?
2023/4/21, Fri.
数百メートル南西の灰色の肌のシラカバが、水の行方を教えていた。私は野原を横切って、少し幅が広くなった川床にたどり着く。細い畦道が蛇のようにくねくねと畑と用水路の間を縫ってつづいている。道幅は二メートルもない。若芽の毛布にいくつか裂け目ができている。泥炭質の土がそこだけ湿り気を帯びて光っている。イノシシが掘り返したのだ。ヒバリが一羽、囀りながら空高く舞い上がる。その歌は息もつかずに春の訪れを告げるが、春はまだ遠く、信ずるに足らないように思われる。初めて水音も聞こえてくる。水はコポコポと優しい音を立てながら小さな森に向かって流れ、ハシバミの茂みの中に消える。私は森の内部の心安らぐ静けさに浸る。ここで大地は強い東風から守られ、まだ去年の灰白色の枯葉を載せている。下草は土にまみれて灰色をしており、チョウチンゴケだけがパセリのように青々としている。卵黄色の花を咲かせる用意のできたセツブンソウが、葉を広げてすっくと立っている。森が明るくなり始める頃――小枝や松毬 [まつかさ] 、そして青黒く光る獣の糞の間に――私はシカの角が落ちているのを見つける。その焦茶色の角はずっしりと重い。私は快い細かい筋と小さな粒々のある、硬い革のような表面や、枝分かれしたなめらかな先端に触れてみる。かつて額骨の突起を飾っていた膨らんだ環の部分には、まだシカの毛が付着している。角はつい最近脱落したばかりにちがいない。純白の根本部分のざらざらした痂皮 [かひ] のような骨組織は、まるで珊瑚石のように鋭く尖っている。角を落とすのにはかなりの力が必要だったにちがいない。まわりに生えるトウヒの樹皮に、(end176)ミミズ腫れのような筋がいくつもついている。その傷口には乳状の樹脂がまるで凍った血のように固まっている。お腹を空かせたシカに、樹皮をきれいにかじり取られている木もある。
一陣の風が梢を揺らし、空が明るくなる。一瞬、太陽の輪が厚い雲の層を通してうっすらと光るのが見える。影がさしたわけでもないのに、たちまちあたりは騒然となり、鳥たちの声が大きくなる。カササギの機械的なお喋り、ズアオアトリの疲れを知らぬ歌、クロウタドリのしゃがれ声、コマドリの憂いに満ちた単調な節。
私が森の外に出ると、一羽のハシボソガラスが舞い上がり、カアカアと鳴きながら、冬大麦の緑色の斑の畑の上を滑るように飛んでは、何度も急降下する。その間その耳障りな声が途切れることはない。風景は変わったように見える。静かで整然としている。まっすぐな粘土質の土の道が、用水路に沿って次の集落までつづいている。そのほとりには葉のない柳の茂みが点々と並んでいる。水中に、いまはもう販売されていないメーカーの火酒の瓶が沈んでいる。道の左手の枯れた藪の中から、赤灰色のキイチゴの枝が何本か突き出ている。鳥の巣が葉のない茂みの中に掛かっている。そしてヒトシベサンザシの低木の根元に、石灰のように白い、打ち砕かれた沢山のカタツムリの殻と石が転がっている。その石の上で、クロウタドリやツグミがカタツムリの柔らかい肉を殻から掘り出したのだ。トラクターの盛り上がったタイヤ跡は雨と雪解け水でふやけていて、私が踏むたびにぐにゃりと潰れる。あちこちの水たまりは周囲の色を吸収したようだ。濡れた粘土と濁った沼の褐色。全体が次第に調和して、色のコントラストが少なくなっていく。ヤマネコヤナギの萌黄色の縁どりのついた枝だけが、小さな銀色の花穂 [かすい] と一緒に冷たい空気の中で震えている。その艶のある毛皮は、べとべとする芽鱗 [がりん] が剝けたばかりだ。
村の入口の標識の少し手前で、流れは分岐する。私はその中でいちばん目立たない、ポッキリヤナギに縁どられた畦道の奥深くに隠れた、細い水路を辿ることにする。ポッキリヤナギはまるで土手に(end177)頭から埋まった不恰好な生き物のように、水辺の藪の中から突き出している。樹冠をつめられ、枝はねじ曲がり、風雨にさらされ空洞化している。折れた箇所からは朽ちた木片がはみ出している。
まもなく道は用水路にぶつかる。地図に書かれている探していた名前の川だ。その流れは蛇行せずに、周囲から離れて東へ向かい、柳に縁どられた、二つの牧草地の間の自然の境界となっている。岸辺の痩せた土の上に、雨に倒されたカヤツリグサが束になっている。流れは製図板に引かれた通りの直線を音もなく辿りながら、次々と南北に分岐する水路へ水を供給する。周りの土地は凍りついたように動きがない。すべてが遠く、すでに何かしら用途が決まっている。耕作地、いまはまだ家畜小屋にひしめいている牛たちの牧草地。風だけが時おり激しく吹いて息を寸断し、嵐さながらに私の歩みを阻む。空にはむくむくと筋肉質の雲が浮かんでいる。どこか遠くから車の往来が聞こえる。
しばらくしてようやくまた目を引く物が出てくる。ミズキとトゲスモモの斜面が耕牧地を囲み、厳しい北東風から守っている。灰褐色の、クロウタドリほどの大きさの鳥の群れが畑の上を飛び、何度も集まって休んでは、些細なことでまた舞い上がる。ノハラツグミだ。古い料理の本に登場する、ビャクシンの実を好む灰色の斑の鳥で、地中海沿岸で越冬してきたのだろう。時おりキアオジも、菜種色の斑模様を見せながら冷たい空気をよぎる。ほとんど気づかないくらいに用水路は水位を上げ、川幅を広げて、水面に鱗のような泡を浮かべながら、機械式の堰の開いた地下牢を通り抜けて流れていく。
やがて車道が近づき、水路を横断する。私は平らな錫灰色のアスファルトに違和感を覚える。車がすごいスピードで通過していく。北の方にはポプラの防風林越しに、コンクリート色の家畜小屋、膿を思わせる緑色のサイロ、セロファンにくるまれた藁束の灰白色のピラミッドが見える。どこかで農業機械の唸る音がする。雪片がちらほら、黄色くなった牧草地のぬかるみに、音もなく降りていく。
私は岸辺の草むらに、鶏の卵ほどの大きさの、茶色い模様のドブ貝を見つける。その内側は真珠色(end178)に光っている。そこからさほど離れていない所で、マガモが水底の餌をあさっている。私が近づくと、都会に暮らすその近縁種に比べてはるかに臆病らしく、不愛想にガアガア、バタバタと騒いで飛び立ち、近くの休耕地に集まって舞い降りる。その足は明るい橙色、畑の灰色の額縁の中で、雄の頭は光の加減により青碧色に変化する。何時間も単色だけを見てきた後で、この鳥たちはエキゾチックなほど色鮮やかに感じられる。
(ユーディット・シャランスキー/細井直子訳『失われたいくつかの物の目録』(河出書房新社、二〇二〇年)、176~179; 「グライフスヴァルト港」)
- 一年前からニュース。
(……)新聞の一面からウクライナの報を読む。マリウポリのさいごの拠点である製鉄所が激しく攻撃されており、ロシア軍は地下貫通爆弾というものをつかったという。地下にまで貫通したあと爆発するものらしく、それで施設はかなり損害を受けたようで、生き残ったアゾフ大隊のにんげんだかが多数のひとびとが瓦礫に埋もれていると証言していた。施設にはウクライナ軍とアゾフ大隊の兵二五〇〇人ほどがのこっていたといい、また子どもをふくむ市民もおおく避難してきていた。マリウポリはもうほぼ全域が制圧されたようで、ロシアとウクライナは市民をザポリージャに逃す「人道回廊」の設置に合意したというが、ロシアからすればもうあたらしい市長も置いてかれらの統治をはじめるつもりのようなので、市民を逃がす必要はないといういいぶんになりそうなものだが。文化面には古川日出男があたらしい小説を書いたという報。カルト集団をとりあつかったものらしく、オウム真理教による地下鉄サリン事件が風化しつつあるいま、とうじの空気を知っているにんげんが書き残しておかなければならないという意識からものしたという。社会面、さいごのページにはヘルソンからリヴィウに避難したひとの証言。ロシア兵は家に押し入って金品などを押収し、体格のよい男性は連行されて、ころされたのか刑務所にいれられたのかだれにもわからない、という。
- 天気と交感。
うえに書いたようにすこしばかりでも外気を浴びようとおもったので上階にあがってベランダに出、しばらく屈伸したり左右に開脚して腰をひねり太もものつけねのほうを刺激したり、前後に開脚して脛のすじをのばしたりした。文句なしの曇天である。雲はきれいに空を白く埋め尽くしていて、上体を左右にひねりながらみあげれば一帯のなかでは西の低みがより白く、すこし高めから天頂まではそれにくらべるとみずいろの気がみえないでもないが、いずれたいした差でもなく総じて白の模様なき平面である。微風がながれて冷たさにむすばず不定のうごきで肌にふれまわりなでていくのがここちよい。自由とおちつきと開放の感覚。ことは皮膚感の問題である。とおくのおとがつたわってくるのもよい。
- (……)さんのブログより。
しかしこういう発表形式の授業をやってみてあらためて思ったのだが、中国の学生たちって本当にずっとスマホをいじっているよなと思う。教師が教壇で話しているにもかかわらずスマホをいじりつづける学生が相当数いるのにはもう慣れたが(この仕事をはじめたばかりのとき、マジかこれ! とびっくりしたものだったし、じぶんの授業がそんなにまずいのだろうかと凹みもしたわけだったが、のちほど同業者らの経験談が寄せられているウェブサイトで、授業中のスマホいじりとカンニングの多さについて経験者のほぼ全員が触れているのを見て、あ、そういうものなんだなと受け入れるようになった)、クラスメイトの発表中も、もっといえばふだんコンビで行動している相棒の発表中ですら、ろくにその話を聞かずスマホをいじりつづけている学生が少なからずいて、ああいうのってそれがきっかけで揉めたりしないんだろうかといつも不思議に思う。最前列に着席している学生らにしても、じぶんたちとそれほど関係の深くない学生の発表時には、発表している学生のその目の前で堂々とスマホをいじっているわけで、たとえば日本語能力のめちゃくちゃ低い発表者の発表をつまらないと感じるのは仕方ないにしても、だからといって堂々とはばかりなく黙殺する、そこにはとんでもない飛躍があるでしょうとこちらなどは思うのだが、どうも中国人社会ではそうでもないようなんだよな、こういう場面には授業外でも本当にしょっちゅう出くわす。コロナ前の話だが、スピーチコンテストの練習がはじまってほどないころ、参加者と指導教師が会議室に集められて、そこで外国語学院のお偉いさんの訓示を聞く形式的な会議があったのだが、おなじテーブルのぐるりを囲んだその席上でお偉いさんの女性教授があれこれずっとなにやら口にしつづけるその正面に座っている(……)先生がテーブルの上に置いたスマホを堂々といじっていたり、あるいは学生らが机の下に隠したスマホをやはりいじっていたりするそのようすを見て、ある程度人数のいる場で、木を隠すなら森の中ではないけれども頭数にまぎれて内職をするのであればまだ理解できる、しかしそのときはおなじ机にお偉いさんとコンテストに参加する学生三名、指導教員としてこちらと(……)さんと(……)先生と(……)先生だけが同席しているという状況だったわけで、え? このシチュエーションで内職すんの? マジで? と心底びっくりしたのだった。これもこの国でたびたび感じる「他者」の不在に通ずる現象かもしれん。
*
「(…)私は愛にとらえられていながら、だれを自分が愛しているのかわからない。私は忠実でも不実でもない。私はいったいだれなのか? 私は自分で私自身の愛のことがわからない。私は愛に満ちた心をもち、が同時にその心は愛のために虚ろなのだ」
(マルティン・ブーバー/田口義弘・訳『忘我の告白』より「フェリード=エド=ディーン・アッタール」)
あなたのもつすべてを火のなかへ投げこむがよい、靴にいたるまで。なにひとつあなたのもつものがなくなったら、屍衣にさえ思いを向けずに裸で火のなかへ身を投じるがよい……。
あなたの内部のものが断念のなかでひとつに集められたなら、そのときあなたは善と悪との彼方にいるだろう。善も悪もあなたにとって存在しなくなるだろうとき、あなたははじめて愛するだろう、そしてあなたはついに、愛のわざである救いにふさわしくなるであろう……。
(マルティン・ブーバー/田口義弘・訳『忘我の告白』より「フェリード=エド=ディーン・アッタール」)
- Garth Cartwright, “‘We paved the way for the Rolling Stones’: Ottilie Patterson, the forgotten first lady of British blues”(2023/4/19, Wed.)(https://www.theguardian.com/music/2023/apr/19/ottilie-patterson-the-forgotten-first-lady-of-british-blues(https://www.theguardian.com/music/2023/apr/19/ottilie-patterson-the-forgotten-first-lady-of-british-blues))




2023/4/20, Thu.
大きな雲の覆いが、頭上に低く重たげにかかっている。かろうじて遠くの方に空が明るんでいる所があり、そこから薄いバラ色がひとすじのぞいて見える。がっしりしたナラの木が数本、柵で囲まれた牧場の向こうにそびえている。大昔に開墾された放牧地の名残だ。窪地に雨水と雪解け水が溜まって湖のようになっている。そこにナラの枝が映っている。トウシンソウに似た淡黄色の草が、その淡青色の水の中から生えている。一羽のセキレイがひょこひょこと水辺を通り、お辞儀をするように尾(end174)羽を低く下げ、羽毛を散らしながら飛び立つ。
表面が凍って硬くなった、まだ三日も経たない三月の雪の名残が、日陰になった芝生の隅や、トラクターのタイヤ跡のくぼみ、干草を発酵させて飼料にするための、白いシートにくるまれた円筒形の塊の陰で光っている。岸辺にはひっくり返った家畜用の餌入れが錆びている。その上にヒトシベサンザシの裸の枝が伸び、その樹皮は硫黄色の地衣類に覆われている。その時、ラッパのような鶴の声が鳴り響く。用水路の向こうに、二羽の鉛色の鳥が巨大な翼を広げて飛び立ち、すぐにまた曲線を描いて着陸の態勢に入る――完璧な調和を保ちつつ、両脚を地面に向かって伸ばしながら――そして三回短く羽ばたいて、すっと着地する。その後まだしばらく響いていた鶴の声は東風にのみ込まれる。唸り声をあげて海から吹いてくるその冷たい風は、薄鼠色のナラの葉を巻き上げる。畑の土はなめらかだ。黒褐色の粘土質の土の塊がそのまま、あるいは柔らかくほぐされて表土に載っている。畝間には菜の花が芽吹いているが、葉の縁はすでに農薬の毒のために脱色したブロンドのように変色している。色彩には生気がなく、光はまるですぐにも夕暮れが訪れるかと思うほど弱々しい。
泥炭に覆われた窪地の風陰 [かざかげ] で、ノロジカの群れが草を食んでいる。私が近づくと、お尻の毛を鏡のように白く光らせて、いっせいに森へ駆け下りていく。円形の沼のほとりに立つ櫓の、骨組みを覆う迷彩柄の布の一部が剝がれて風にはためいている。そこからさほど遠くないところ、キイチゴやニワトコ、コケモモの葉のない茂みの前に、苔むしたコンクリート板が山と積まれている。鉄筋の穴から錆びた金具が突き出ている。安物の鋼がいまや雨ざらしになっている。多孔質のコンクリートブロックには、藍墨色 [あいずみいろ] の苔が繁茂している。その向こうに、葉のない藪に守られるように、氷期にできた穴にとろりとした緑色の沼がひっそりと憩っている。ヒキガエルやトノサマガエル、スズガエルの産卵場所だ。彼らは身を潜めて繁殖の合図を待っている。冬枯れの草は蠟色に干からび、色褪せている。ただキンポウゲだけが、湿った黒土の中から元気いっぱいに濃い緑色の葉を出している。
(ユーディット・シャランスキー/細井直子訳『失われたいくつかの物の目録』(河出書房新社、二〇二〇年)、174~175; 「グライフスヴァルト港」)
- 一年前から。
(……)うがいや洗顔、用足しをしてもどってくるとまたあおむけになって南直哉『「正法眼蔵」を読む』を読んだ。南直哉の理解(を要約するこちらの理解)によれば、道元の説く思想の要点は、この世界に本質や実体などの同一的で究極的な根拠はなくすべてが関係性の相互作用のうちから生じてくるという空=無常=縁起の次元を修行という具体的かつ身体的な実践において認識し、その認識にもとづいて現状の自己を解体するとともにあたらしくつくりなおし再構成的に生成させていくことにある、というわけで、だからやはり主体における永久革命論みたいな質感を帯びるんだよな、とおもった。この本でも、引かれている『正法眼蔵』じたいにおいても、いまのところ、それをたえまなくつづけていくのだ、というような、永久反復の様相は直接述べられてはいないとおもうが。本質をもたず条件におうじて可変的であるがゆえにいくらでも変わっていくことができるという自由と革命の思想にはそれはそれでもちろん魅力があるけれど、そのすがすがしく楽観的な野放図さはユートピア的なのかディストピア的なのかわからないし、現実いろいろ制約はあるわけで、それだけに乗るわけにもいかないだろう。
*
坂を行くあいだにウグイスの声を朗々ときいた。こちらには初音だが、たぶんもうすこしまえから鳴きだしていただろう。おもてみちまで抜けて通りをわたったところの家に藤の花が咲きだしていた。街道沿いをしばらく行けば公園の桜木はもちろんもう花は消えて若緑一色の葉桜で、繁りはまださほどでないが幹のわかれめあたりにあつまった葉叢などみずをそそぎこまれたようにいろがあきらかで、初夏を待つ身とにおわしく充実している。裏へ折れて正面の公団では垣根のむこうに白のハナミズキがちいさくいっぽん咲き群れていて、曲がってさいしょの家の庭でもさきごろから盛っているピンク色の同種がもう弱ってもおかしくなさそうなのにおとろえをみせず落花のひとつもなく、ちかく接しあった群れをくずさずにはなやかないろどりに浮かんでいる。きょうは吹くというほどのものはなく、耳の穴のまえにおとも立たず、風はながれのゆるやかさだった。庭の低木であれ丘のやわらかな濃淡であれそのへんに生えている雑草であれ、どんなみどりもみどりであればおしなべて、絵の具をそこに直に塗られたような密なめざましさに現成している。ひろい空き地の縁ではもう穂がひろがらずほそって黄みがかったススキが、巨大化したネコジャラシのようにのびあがって乾いていた。
(……)をわたってすこし行ったさき、(……)の駐車スペース的な土地(もくもくとしたおおきな常緑樹と車庫らしきものがある)と一軒のあいだの小敷地にチューリップをみた。地面は草が覆い、ネギボウズもなんぼんか立って、そこの端にあるユキヤナギはもう白い細片をほとんどたもたず茶色によごれて溶けきる寸前だった。(……)に寄って小用。出ると男子高校生の三人、ついで女子高生ふたりがみちを来ており順々にぬかされる。女子のほうからは、あんまりかっこよすぎても逆にダサいっていうか、とまずきこえて、アイドルのはなしでもしているのだろうかとおもいつつ、いまの時代や若者の感性を象徴するひとことのようにもきいたのだが、どうもアイドルのはなしではなく、おそらくダンス部かなにかで校庭かどこかでやる演目を相談しているような雰囲気だった。時期から推して部活紹介とかか? 細道が切れてあいまにはさまる横道からつぎの細道にはいっていくそのあたりでひとりがうたをくちずさみだし、その曲めっちゃいいともうひとりが同じていた。ある種の女子高生というのはなかまとそとをあるいているあいだ、ごくしぜんに、ふつうのこととしてうたをうたいだす。すばらしい。
- 「読みかえし2」より。
1410
『創世記』は「はじめに神は天地を創造された」という言葉ではじまる。すなわち、天地創造以前の神については一言も触れていない。「天地創造以前に神はなにをしていたのか、(end92)という問いは意味をなさない」とは、アウグスティヌス(三五四~四三〇)も言っていることである(『告白』第一一巻第一三章)。なぜなら、時間は天地創造とともに始まったのであるから、「以前」も「以後」もすべて天地創造以後において意味のあることがらだからである、と。
このことは、いちおうアウグスティヌスの言うとおりだとしておこう。しかし、とにかく天地創造以前の神への言及がないことの意味はなんであろうか。それは、イスラエル人の神が、つねに世界との相関関係のうちで語られるということである。世界のないところで唯一独存する神というものは考えられていない。彼らの神は、パルメニデスの存在のように不変不動の永遠性のうちで微動だにしない絶対者ではないのである。イスラエルの神は他者を呼び求める神なのである。
こうして、この神は言葉によって「世界」を無から呼び出した。このことの意味はなんであろうか。
まず、この神は他者を呼び迎えるというしかたで、自己充足から脱出する神である。「他者を呼び迎えること」とは愛であるから、この神は本質的に「愛」なのである。愛は絶対的に他者を必要とする。だから、この神は「無から」でさえ他者を創造するほど徹底的に愛なのである。モーセがシナイ山で神の名をたずねたとき、神の自己啓示として語られた「私はあなたたちと共にあろうとする者である」(『出エジプト記』三の一四)という言葉は、この神の(end93)本質をあらわしている。
第二に、神は「言葉」を発して世界を創造した。バビロニアやギリシアの神話におけるように、原初の混沌から分裂と結合によって世界が生成するという物語とは、この「言葉による創造」ははなはだしく異なっている。このことの意味はなにか。言葉は本来応答する者を期待して発せられるものである。それゆえ、神は応答する者を期待して世界を創造したのである。しかし、人間以外の自然的な諸存在者は厳密な意味で「応答するもの」とは言われえないだろう。それだから、言葉を語る人間が、世界を代表して神に応答する者として、世界創造の意味を担っているのである。
後に、二〇世紀になって、ハイデガー(一八八九~一九七六)が、「人間の使命は、存在の声を聞きとり、それを言葉によって歌うことである」と言ったとき、この思想のはるかな淵源が、このヘブライの神への応答にあった、という解釈も存在するのである。
いずれにしても、神はすべての自然物を創り終えた後、最後に人間を創り、「地に満ちて地を従わせよ、海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよ」(『創世記』一の二八)と言ったのだが、その意味は、人間が全被造物の代表者であり、したがって、それらのものに責任を負いながら、神の呼びかけに応答する者である、という点にあるだろう。すなわち、人間は自然の一部分であると同時に、自然を超えてゆく者という二重の性格をもつのである。(end94)
第三に、神が世界を「無から」創造したということの意味である。「無から」とは、世界には固有の質料がないということだ。ギリシアやバビロニアの神話における原初の混沌のようなものにせよ、プラトンの場所(コーラー)にせよ、アリストテレスの第一質料(ヒュレー)にせよ、そこから万物が生成する不滅の根源的素材はなにもないということである。このことは、もちろん世界には本来固有の存在根拠がないということを意味しているが、同時に、神は世界から絶対的に断絶しており、世界を超越しており、世界内のいかなる存在者にも帰属しない、ということをも含意している。
すなわち、神に対する世界とは、神に対する無なのである。それゆえ、私たちが存在(現代哲学の言い方では現象)と呼ぶものが、時間・空間・形象に制約された世界内の存在者としてしか了解されえないとすれば、神は「存在」ではなく、「存在のかなた」でなければならない、ということにほかならない。
(岩田靖夫『ヨーロッパ思想入門』(岩波ジュニア新書、二〇〇三年)、92~95)
1411
天地創造の最後に、「神は自分にかたどって人を創造された」(『創世記』一の二七)と記されている。だから、人間は神に似ているのである。
では、神に似るとはどういうことか。神は切に他者を求めて世界を創造した。そうであれ(end95)ば、人間も本質的に他者を求める者だということである。このことが「愛」という言葉で表現されるのであれば、人間は本質的に愛する者なのである。「神は愛である」とは後に新約聖書でヨハネも強調していることだが、そうであれば、神に似て創られた人間も愛なのである。
ところで、愛しうる者は自由な者でなければならない。選びうる者、否を言いうる者、拒否しうる者、憎みうる者でなければ、愛することはできない。なぜなら、けっして否を言いえない者とは、因果法則にしたがって必然的に運動する無機的な自然物、あるいは機械のごときものであり、いわばロボットであり、せいぜいのところ奴隷であるにすぎないからである。
それゆえ、愛し合う者どうしは自由意志の根源から相手を肯定するのであって、けっして支配・被支配の関係にあってはならない。なぜなら、支配・被支配の関係はそれ自体が愛を破壊しているからである。だから、切に愛を求めた神は、自分を拒否しうる者、自分を否定しうる者、すなわち罪を犯しうる者を創りだしたのである。なぜなら、ロボットをつくりだしても、愛の相手にはならないからである。けっして否を言わない応答機械をつくりだしても、それは他者ではありえず、呼びかけはむなしく虚空のうちに消滅してしまうであろう。
ここに、人間の創造の恐るべき秘密があるにちがいない。人間の愛を切に求めた神は、愛(end96)を求めたがゆえに、ついに、人間を自分と対等な者にまでしてしまうという、パウロの表現を使えば、「神の愚かさ」にまでいたってしまったのだ。
「神の似姿」としての人間のもう一つの特徴として、人間の唯一性、絶対性、現在流行の表現を使えば、「かけがえのなさ」があげられるであろう。神が唯一、絶対なる者であるように、その似姿である人間も、一人一人が唯一、絶対なる者なのである。
このことの意味は、いかなる分類原則にしたがうにせよ、人間を類的普遍者として一括してはならないという点にある。「自由な者」であるということそれ自体が、そのような存在者には類的普遍者などというものはありえない、ということをすでに含意しているのである。自由な者である他者を、自分の同類としてくくりうる根拠はどこにもない。
このことを無視して、人間を、理想によるにせよ、思想によるにせよ、宗教によるにせよ、イデオロギーによるにせよ、類的に全体化して一括統制することが、二〇世紀に荒れ狂った全体主義なのである。一人一人がみな異なった絶対者なのだ。
愛とは、一人の絶対者が一人の絶対者へと呼びかけることである。類的な同一性の中へ相手を同化することではない。それゆえ、罪とは、他者のこの呼びかけの拒否以外のものではない。他者との対面を拒否すること、他者を避けること、あるいは逆に、他者を奴隷化すること、言いかえれば、自己を絶対化すること、それが根源の罪であるだろう。同化ではなく、(end97)呼びかけである。神が人間を呼んだように、人間も人間を呼び、それを通して神を呼ぶのである。それが、「神の似姿」であることの意味である。
(岩田靖夫『ヨーロッパ思想入門』(岩波ジュニア新書、二〇〇三年)、95~98)
- Guardian staff and agencies, “Russia-Ukraine war at a glance: what we know on day 421 of the invasion”(2023/4/20, Thu.)(https://www.theguardian.com/world/2023/apr/20/russia-ukraine-war-at-a-glance-what-we-know-on-day-421-of-the-invasion(https://www.theguardian.com/world/2023/apr/20/russia-ukraine-war-at-a-glance-what-we-know-on-day-421-of-the-invasion))
The European Commission is proposing €100m (£88m) in compensation for EU farmers affected by the recent influx of Ukrainian grain as well as restrictions on selling wheat and maize in affected countries, in a move to calm tensions with central and eastern Europe. Ursula von der Leyen, the head of the commission, has written to the leaders of Bulgaria, Hungary, Poland, Romania and Slovakia, setting out support measures after four of those countries banned the import or sale of grain and other food products inside their borders earlier this week. Bulgaria had confirmed its temporary halt on Wednesday.
*
A joint investigation by the public broadcasters of several Nordic countries alleges that Russia has established a programme using spy ships disguised as fishing vessels aimed at giving it the capability to attack windfarms and communications cables in the North Sea.
The Kremlin critic Ilya Yashin has lost an appeal against what his supporters say was a politically motivated decision to jail him for eight and a half years – in a case that has echoes of Monday’s jailing of Vladimir Kara-Murza. The former Moscow councillor’s appeal was rejected as authorities continue to repress freedoms in Russia, with independent media shut down and leading opposition figures behind bars or in exile.
Russia has said it summoned the UK ambassador Deborah Bronnert on Tuesday after she criticised the 25-year jail term given to Kara-Murza. She spoke to reporters outside Moscow city court alongside the US and Canadian ambassadors, describing the sentence as “shocking” and called for Kara-Murza, who holds joint UK and Russian citizenship, to be released immediately.
- Murong Xuecun, “China’s ‘zero Covid’ policy was a mass imprisonment campaign”(2023/4/18, Tue.)(https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/apr/18/china-zero-covid-policy-xi-jinping(https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/apr/18/china-zero-covid-policy-xi-jinping))。これはけっこうな記事で、いまさらではあるけれど中国がいったいどういう国なのかというのがじつにまざまざとよくわかる。ほんとうは著作権上だめなんだろうがしたに全文うつしてしまう。Murong Xuecunというなまえは漢字だと慕容雪村となるらしい。
In one week last December, five members of Guan Yao’s family in Beijing died, including his father, his father-in-law and his grandmother. In an interview with a journalist, Guan, who lives in California, appeared powerless and dejected. Yet – for reasons that anyone from China understands – he chose his words carefully. Avoiding directly mentioning the Chinese government, he referred only to an ambiguous “them”. “It is difficult to understand,” Guan said, “why they abruptly lifted all restrictions.”
If you choose to believe official Chinese government documents, the deaths of Guan’s five relatives had nothing to do with Covid. They may have been infected with Covid, but government rules – rules that can’t be made public and can’t be questioned – required that doctors who issue death certificates come up with other causes of death. Guan’s uncle died of Parkinson’s, his grandmother of kidney failure.
During this time, not a single citizen of China, a country of 1.3 billion people, officially died of Covid. A tidal wave of coronavirus was inundating cities and villages, leaving piles of corpses in mortuaries; crematoria working day and night could not keep up with demand. But in order to prove its accomplishments in the anti-Covid battle the Chinese government persisted for almost two weeks with its claim that no one had died of Covid.
This is nothing new. From the moment Covid-19 first appeared, the Chinese government assiduously controlled the mortality figures in the same way an unfaithful husband under interrogation by his wife at first denies everything. Then, when he can no longer continue with his denials, he tries to limit the damage. “Um, all right, but it was just once or twice.”
No wife ever believes such lies; neither do the Chinese people. Supporters of the Chinese Communist party tend to walk a careful line. A businessman friend is an example. “The government’s numbers are not necessarily accurate, but you have to look at the positive side,” he told me. “They did it for us.”
Not that you need to be concerned for the Chinese government. It is not suffering a crisis of confidence. China has hordes of police, both uniformed and plainclothed, with ample ability to make people believe the government. A secret policeman once said to me directly: “You don’t believe it, but what are you gonna do about it?”
My businessman friend is not alone. Inside China, government-controlled media and covert propaganda officers are sparing no efforts to sing the praises of the pandemic-prevention policies: “Thank you, Chairman Xi! Thanks to the Communist party!” “Our policy has the approval of the people, and it will stand the test of history.” “The state protected us for three years. The government did its utmost!”
Outside China, some western observers employ “although … but … however” syntax to express their own often fulsome support: Although Xi’s policies may have seemed a little extreme, the initiatives characterized by the People’s Daily as correct, scientific and effective not only reduced the transmission of the virus but also reduced the death rate to well below that of other countries …
I disagree. As I see it, Xi Jinping’s measures have very little to do with public health. They have been a masterclass in dictatorship with an underlying theme of “how to more effectively control society after a disaster strikes”. The primary objective is not protecting people’s lives and health, but protecting and expanding his power as much as possible. Totalitarian pandemic-prevention policies have no obvious efficacy other than to wreak havoc on hundreds of millions of people. Such policies do not merit any praise. They are the source of an anti-scientific humanitarian catastrophe.
Before 7 December 2022, Xi’s government pushed a “zero Covid” policy. That is not as benign as it sounds. In essence, it is a mass imprisonment campaign. In my book Deadly Quiet City: True Stories from Wuhan, I report on how the Chinese government turned Wuhan, a city of 11 million people, into a massive and miserable prison.
Then Xi obviously realized that the anti-pandemic measures brought him benefits. He doggedly expanded the policy to encompass the whole country. In many places, just one positive case or sometimes not a single positive case, resulted in a district or even an entire city being completely locked down, transportation links severed, shops closed, and residents confined behind layers of fences topped with razor wire. No one could leave their homes even to exercise their most basic of rights – the right to food and to seek medical attention.
This is how the Chinese government accumulated ever more power. No warrants are needed to storm into residences. Thousands and tens of thousands of people can be forced into isolation at any time, transported to facilities resembling concentration camps with insufficient food and a total lack of privacy. If anyone is brave enough to resist, a succession of punishments relentlessly rains down – policemen, government officials and so-called volunteers, often in full white PPE, need no authorization to surround and kick and punch their victim, who is then dragged to jail or publicly humiliated.
A notorious photograph from 17 November 2022 showed two young women who were beaten and humiliated after allegedly refusing to cooperate with pandemic-prevention officers: one lay prone, bound hand and foot; the other, hands tied together, was forced to kneel.
Punishments were not limited to the purported offenders. Entire families were dragged into the maelstrom. In Shanghai, in May 2022, police threatened a youth who expressed mild objections: “Your punishment will affect you for three generations!” The youth retorted loud and clear: “We are the last generation, thank you very much!”
China’s pandemic-prevention policies led to countless deaths and tragedies: ill seniors killing themselves because they couldn’t get medical treatment; youth jumping off buildings because they couldn’t make a living; unborn babies dying in their mother’s wombs while their mothers awaited treatment. When a fire broke out in an apartment building in the far western city of Urumqi, on 24 November 2022, the pandemic prevention policy of turning residential zones into prisons prevented fire engines gaining access. Residents struggled to escape the inferno. Ten died and many more were injured.
Two weeks later, on 7 December, the government made an unexpected 180-degree turn. No more city-wide lockdowns, no more forced PCR testing. In fact, no effective mitigation measures at all. It was like a flood control officer opening the floodgates and standing on high ground to coldly watch the raging torrent surge towards cities and villages.
In the following days incalculable numbers of people died, including respected scholars, journalists, film directors, celebrities and even some high-level Communist officials and military officers. Even in a wealthy city like Shanghai, there was a severe shortage of medicines, including the most basic fever medications and painkillers. Every hospital was overcrowded. Doctors and nurses – some themselves infected – endured the wailing and moaning of patients as they filled out a cascade of death certificates.
This was when Guan Yao’s relatives died. There were so many deaths that cremation fees doubled and tripled. His family spent 30,000 yuan – about $4,300 – for his father’s cremation. His grandmother had to wait 10 days for cremation. Hospital and mortuary freezers were filled with bodies. In many cities, local governments requisitioned seafood and meat-storage freezers to hold the deluge of corpses.
And then there are the remote townships and hamlets that on a map of China are like a tiny fold in the Mariana Trench where there are no lights and where the party’s kindness never reaches. According to investigations by citizen journalists, many rural villages are experiencing widespread infections but are virtually without medicine. Impoverished farmers scramble like their Stone Age ancestors for herbal remedies. Some have never heard of coronavirus or the Omicron subvariant and have no idea how to treat them. They believe that a broth made with pears can suppress coughing; that is all they have to fight the virus, and in some remote hamlets old people struggle to shake the leaves and flowers off loquat trees in the belief they will save their lives.
Yet the endless tide of death and suffering has so far been insufficient to prove to Xi’s government that any mistakes were made. In fact, party officials hold grand celebrations and publish volumes of self-congratulatory articles. They know that in an autocratic society, the truth is what you say it is.
Four months ago, Xi broke with convention and got his wish for a third term. Soon he, like Chairman Mao Zedong, will in effect become emperor for life. Over the past 10 years and especially in the last three years of Covid, this overconfident author (Xi has more than 100 books to his name) and ruler has fully demonstrated his ability to wreak suffering. In the future, how much suffering at his hand will China and the whole world experience?
To ring in the new year, Xi appeared on TV wearing a dark blue suit with a red tie. He smiled wryly and announced a line that he may not himself believe: “We have always insisted upon the primacy of the people and their lives …”
A few days later, the Chinese government entered a new round of negotiations with Pfizer. For the past three years, the Chinese government refused to import efficacious western coronavirus vaccines and treatments while strenuously pushing domestic vaccines and promoting herbal concoctions.
This latest round of negotiations – which many believe was just for show – not unexpectedly failed because the Chinese government says Paxlovid is too expensive. Pfizer’s CEO, Albert Bourla, responded: “They have the second largest economy in the world, and I don’t think that they should pay less than El Salvador.”
Heated discussion in China ensued. One of my friends had an interesting point of view. “It’s not about the price of the Pfizer drug.” To the Chinese government, “our lives are not worth the money”.

―――――
- 日記読み: 2022/4/20, Wed.
- 「読みかえし2」: 1398 - 1419
- 「ことば」: 1 - 2, 3
2023/4/19, Wed.
困難なのは水源を見つけることではなく、それを見分けることだ。私は牧草地の前に立っている。持ってきた地図は役に立たない。私の目の前には用水路が流れている。水はさほど深くなく、溝幅は(end173)せいぜい五十センチメートル。水面はところどころ穴の開いた黄緑色のアオウキクサの絨毯に覆われ、ほとりには麦わらのような薄黄色のスゲが生えている。地中深くから水が湧き出ていると思われる所にだけ、緑色の苔が繁茂している。何を期待していたのだろう。ほとばしる泉? 案内板? 私はもう一度地図に目を落とし、青いほつれた線を探す。それは緑色で示された森林地帯の下にある、卵殻色 [らんからいろ] の広い部分から始まっている。水源はこの上の方の、何軒かの家の裏手に延びる山林を探すべきかもしれない。この家々のおかげでここは村落になっており、私はタクシーの運転手にその名前を告げることができたのだった。運転手はきっと、私がここに何の用があるのかと訝しく思ったにちがいない。しかも聖土曜日に。だが好奇心だけでは、このあたりの人の口を開かせることはできない。ここの人々は真面目で無関心――まるで名状しがたい苦悩にのみ込まれでもしたかのように――そしてこの土地の風景と同じく、言葉なしでもやっていけるのだった。
(ユーディット・シャランスキー/細井直子訳『失われたいくつかの物の目録』(河出書房新社、二〇二〇年)、173~174; 「グライフスヴァルト港」)
- 一年前からニュース。
(……)新聞一面にはロシア軍がウクライナ全土三一五箇所にミサイル攻撃をおこなったとの報。事前に一〇〇箇所ほどに攻撃すると通告していたらしいが、じっさいにはその三倍になったと。マリウポリはもうほぼ制圧されたようすだが製鉄所を拠点にウクライナ軍とアゾフ大隊の一〇〇〇人ほどが抵抗をつづけており、投降しなければ全滅させるというロシア軍の最後通告も拒否して抗戦をえらんだ。市民らも一〇〇〇人ほどが避難して生活しているらしい。というのもこの製鉄所の地下にはソ連時代につくられたひろい領域があって(図からすると複数階層になっているようだった)、園芸所とかカフェとかもそなえられているといい、市内のほかの地下施設にもつながっているとか。ロシアがわはあたらしい市長の就任をいっぽうてきに発表しており、かんぜんな制圧を待たずに統治をはじめるもようと。
- 「読みかえし2」より。
Ian Garner, “How Putin is preparing children to ‘die for the motherland’”(2022/11/23, Wed.)(https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/nov/23/how-putin-is-preparing-children-to-die-for-the-motherland(https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/nov/23/how-putin-is-preparing-children-to-die-for-the-motherland))
1382
But the regime is also turbocharging indoctrination efforts aimed at its youngest subjects. This includes well-worn tactics such as closing off social media and online dissent, and rolling out propaganda lessons in schools. But its most effective tool may be a myriad of new youth groups that introduce children to the Russian state’s world of constant war with a dazzling barrage of social media infotainment.
The biggest such organisation is the Youth Army, established in 2016 under the defence minister, Sergei Shoigu, with the explicit intention of preparing children for careers in the state or military apparatus. It is fronted not by a greying politician, or career soldier, but by the popular 25-year-old Olympic and World Championship gymnast Nikita Nagornyy. Charismatic and handsome, as well as hugely popular on social media, Nagornyy uses influencer-style videos and posts to spread the state’s gospel.
*
Equal parts Instagram influencer, teen heart-throb, and chief scout, Nagornyy is the embodiment of the state’s vision for its youth. He is the perfect role model for a 21st-century paramilitary movement. PR photos show him visiting “veterans” of the war in Ukraine, which Nagornyy has repeatedly praised. In turn, his young followers swamp anyone who steps out of line in comment threads: “Go to Ukraine! We don’t need fascists here! Bon voyage!” All over Russia, groups of “young soldiers” clad in distinctive red berets and khaki uniforms practise military manoeuvres and firing guns, attend lessons on patriotic history and gather aid for the “ethnic Russians” the state purports to be rescuing in Ukraine.
A network of such influencers mirrors Nagornyy’s feeds. The 21-year-old champion skier Veronika Stepanova, for instance, posts about her life as an athlete today, as a teen Youth Army member in the past, and about politics and the war in Ukraine. When a Youth Army “veteran” such as Stepanova praises Putin while receiving a state award, she links her enviable lifestyle, the Youth Army and the regime.
The state has thrown massive political and financial support behind the Youth Army project, and it appears to be paying off. Last year a 185m federal subsidy was announced, and the group is growing rapidly. A million children are already members, and enrolment is projected to hit 20% of the school-age population by 2030.
Membership is painted as an enjoyable way to make friends and attain an influencer-like lifestyle. The Youth Army’s official website is packed with uniformed cartoon characters, warlike video game clips and soft-focus images of smiling “soldiers”. Using the group’s social media feeds and official app, children can play games and photograph themselves completing “patriotic” activities – such as visiting war memorials – to win prizes. Many of the young recruits imitate the methods of Nagornyy and the Youth Army by incorporating their Youth Army participation into their carefully curated social media lives – in particular on TikTok, which, despite an official ban, remains widely popular among Russian teens.
The state promises power, self-actualisation and, above all, social belonging. The apathetic and apolitical are left to gaze at this fantasy world from the outside. A series of Youth Army members and leaders I interviewed this summer were unequivocal: joining up wasn’t a totalitarian imposition; it was a proactive choice to belong to a patriotic community. One regional leader told me that his group could barely cope with the number of applications received since 24 February.
But the Youth Army isn’t an ordinary army cadet group, and patriotic social media chatter is not idle talk. Its members are being taught “to die for the motherland”. They learn serious military skills in classrooms and summer training camps. The Russian media whip up expectations about their military capabilities: “The only reason the Youth Army is on the EU’s sanctions list is the west’s fear of Russian children!”
As the state pivots its propaganda away from the measured inculcation of apathy and toward proactive indoctrination, children as young as six learn to speak the language of war: “I want to defend my country and my loved ones,” one new elementary-aged recruit confidently declared to a local TV journalist. And older children must live its reality. Some of the programme’s graduates are already at the front. Online tributes to the former “youth soldiers” who have “died a hero’s death” in Ukraine reify these young men’s deaths, linking their lives to the unattainable ideal of Nagornyy, to the curated Instagram feeds of “young soldiers,” and finally to the paths that Russia’s children are being taught to follow more widely: join up, train in the military arts, discover a sense of community and your perfect self, prepare to defend the motherland.
- パウル・ツェランも。さいしょの「饗宴」というのは冒頭のフレーズをあらためて読んだとたんに、これはなんかいいかも、よくわからんがすごいかもという感覚が立った。
1387
饗宴
夜が誘惑の高い梁の間のいくつもの瓶から空けれますように、
敷居に歯で溝がつけられ、朝の前に 怒りの発作の種が播かれますように――
ぼくたちには おそらくまだ苔が丈高く伸びるだろう、水車小屋からかれらがここに来る前に、
ひそやかな穀物を ぼくたち かれらのゆっくりとした歯車のもとで見つけようと……毒をもった空たちの下では 別の茎たちはおそらくもっと黄灰色だろう、
夢は こことは ぼくたちが快楽を賭けて賽を振るところとは異なって 造り出されるだろう、
こことは 暗闇のなかで 忘却と不思議が交換されるところとは、
すべてが 一時間しか有効でなく そして ぼくたちによって舌鼓みを打って吐き出さ(end44)れ、
輝いている櫃たちの中の窓たちの貪欲な水のなかに投げつけられるところとは異なって―――
人間の道路の上では すべては 雲を讃えてはじける!そこでお前たちは 外套にくるまり そしてぼくと一緒にテーブルの上にのぼれ――
杯たちの只中で 立ったままでいる以外 どうやって眠ることができよう?
ゆっくりとした歯車である誰のために ぼくたちはまだ夢を乾杯するのだろう?(中村朝子訳『パウル・ツェラン全詩集 第一巻』(青土社、一九九二年)、44~45; 『罌粟と記憶』(一九五二))
1390
海からの石
ぼくたちの世界の白い心、暴力はなく ぼくたちはそれを今日 黄ばんだとうもろこしの葉の時刻に失った――
丸い糸玉、そういう風に それは ぼくたちの手から軽々と転がった。
そういう風に ぼくたちには 紡ぐために 新しい赤い眠りの羊毛が 夢の砂の墓場の傍に残された――
もはや心ではない、けれどおそらく深みからきた石の頭髪が、
貝や波を想っているその額の乏しい飾りが。多分、あの街の門口で 一つの夜の意志がその石を空中に高めるだろう、
石の東の目は 石に ぼくたちが横たわる家のうえで 話してきかせるだろう、
口もとの海の黒さと 髪にさしたオランダからのチューリップについて。(end48)
かれらはその石に先立って槍をかかげていく、そういう風に ぼくたちは夢をかかげていった、そういう風に ぼくたちからぼくたちの
世界の白い心が転がり落ちたのだ。そういう風に 縮れた
紡ぎ糸が 石の頭のまわりに生まれたのだ――奇妙な羊毛、
心のかわりに 美しく。おお 来てそして消え去った鼓動! 終わりあるもののなかで ヴェールが翻る。
(中村朝子訳『パウル・ツェラン全詩集 第一巻』(青土社、一九九二年)、48~49; 『罌粟と記憶』(一九五二))
1391
夜の光
一番明るく燃えたのは ぼくの夕べの恋人の髪――
彼女にぼくは 一番軽い木でできた柩を送る。
そのまわりは ぼくたちがローマで夢を見た寝台のように 波立つ、
それは ぼくのように 白い鬘をかぶり そしてかすれた声で語る、
それは話すのだ、ぼくのように、ぼくが心たちに入ることを許すとき、
それは知っているのだ、愛について歌うフランスの歌を、それをぼくは秋に歌った。
旅の途上に晩い国にとどまり 朝に宛てて手紙を書いたときに。一叟の美しい小舟だ その柩は、様々な感情の木材から彫られて。
ぼくもまた それにのって血の流れを下っていった、お前の目よりも若かった時に。
いま お前は 三月の雪につつまれた一羽の死んだ小鳥のように若い、(end55)
いま それは お前のもとに来て そのフランスの歌を歌う。
お前たちは軽い――お前たちはぼくの春を最期まで眠る。
ぼくはもっと軽い――
ぼくは見知らぬ者たちの前で歌う。(中村朝子訳『パウル・ツェラン全詩集 第一巻』(青土社、一九九二年)、55~56; 『罌粟と記憶』(一九五二))
1395
晩く そして 深く
黄金の言葉のように意地悪く この夜は始まる。
ぼくたちは啞の人々の林檎を食べる。
ぼくたちはそれぞれの星に喜んで委ねる仕事をする、
ぼくたちはぼくたちの菩提樹の秋のなかに 物想う旗の赤さとなって立つ、
南方から来た燃えている客となって。
ぼくたちは誓う キリストに 新しき人にかけて 塵を塵と、
鳥たちをさまよう靴と、
ぼくたちの心を水の中の階と契らせることを。
ぼくたちは世界に砂の神聖な誓いを誓う、
ぼくたちはそれを喜んで誓う、
ぼくたちは夢のない眠りの屋根から大声でそれを誓い(end62)
そして 時の白い髪を振る……かれらは叫ぶ、「お前たちは冒瀆している!」と。
ぼくたちはそれをとうに知っている。
ぼくたちはそれをとうに知っている、けれどそれがどうしたというのだ?
お前たちは死のひき臼で 約束の白い粉を挽く、
お前たちはそれを ぼくたちの兄弟たちと姉妹たちの前に置く―ぼくたちは時の白い髪を振る。
お前たちはぼくたちに警告する、「お前たちは冒瀆している!」と。
ぼくたちはそれをよく知っている、
ぼくたちのうえに罪が来るように。
あらゆる警告のしるしの罪がぼくたちのうえに来るように、
ごぼごぼと音を立てる海が
甲冑に身をかためて向きを変えた突風が(end63)
真夜中のような昼が来るように、
決していまだかつてなかったものが来るように!ひとりの人間が墓から来るように。
- (……)さんのブログから。したのラカンの言はすばらしいとおもうが、「何も理解できないものが希望を可能にする」というより、恐怖と拒絶を呼ぶことがままあるのが現今の世だなあともおもう。
ラカンはしばしば、彼がそのような難しさをどれだけ重要と考えているか述べている。たとえば、セミネール第18巻における『エクリ』についての見解を見られたい。「多くのひとたちが躊躇うことなく私に「何ひとつとして分からない」と言っていた。それだけでもたいしたものだと気づいてほしい。何も理解できないものが希望を可能にする。それはあなたがその理解できないものに触発されているしるしなのだ。だからあなたが何も理解できなかったのは良いことである。なぜならあなたは、自分の頭のなかにすでに確かにあったこと以外、決して何も理解できないからだ」(…)。
(ブルース・フィンク/上尾真道、小倉拓也、渋谷亮・訳『「エクリ」を読む 文字に添って』 p.245)
- したの記述は古井由吉が『詩への小路』のさいしょの章で紹介していた。ブーバーの名も出典としてあがっていた気がする。ドイツ語原本からじぶんで訳したのだろう。
アラファート巡礼月の祭のさいに彼は語った、「おお、愚かな者たちに道を示されるかたよ!」そして彼は、すべての人びとが祈っているのを見ると、ある丘の上に登って人びとの姿を眺めたが、人びとがみなもとの場所にもどったとき、自分の身を打ちたたきながら叫んだ、「崇高なる主よ、あなたが純なるかたであることを私は知っています。あなたは賞賛する者たちの賞賛に汚れず、賛美する者たちのあらゆる賛美、思考する者たちのあらゆる思考に汚れることなく純であられます。わが神よ! 私にはあなたを賞めたたえるという義務が果たしえないことを、あなたはご存じです。私にかわってどうかみずから自分を賞めたたえてください、それこそが真の賞賛なのですから。」
(マルティン・ブーバー/田口義弘・訳『忘我の告白』より「フサイン・アル・ハッラージュについて」)
「神を探し求める者は、懺悔の影のなかに、神に探し求められる者は、無垢の影のなかに坐っている。」
「神を探し求める者の走行は、神の啓示に先立って駆け、神に探し求められる者の走行は、神の啓示によって追いこされる。」
(マルティン・ブーバー/田口義弘・訳『忘我の告白』より「フサイン・アル・ハッラージュについて」)
- せっかくなので『詩への小路』のほうも。
――崇高なる神よ、私は知っている、あなたは純白だ。そして私は言いたい。あなたは人の讃美する、すべての讃美にも染まらない。人の礼讃する、すべての礼讃にも染まらない。人の思惟する、すべての思惟にも染まらない。神よ、あなたは知っている、私には称賛のつとめが果たせない。私に代って、御自身で御自身をほめたたえ給わんことを。それこそまことの称賛。
(古井由吉『詩への小路 ドゥイノの悲歌』(講談社文芸文庫、二〇二〇年)、12; 「1 ふたつの処刑詩」; フセイン・アル・ハラージ)
――神を探す者は、啓示の先を駈ける。神が探す者は、啓示がその駈足を追い抜く。
(古井由吉『詩への小路 ドゥイノの悲歌』(講談社文芸文庫、二〇二〇年)、13; 「1 ふたつの処刑詩」; フセイン・アル・ハラージ)
- Guardian staff and agencies, “Russia-Ukraine war at a glance: what we know on day 420 of the invasion”(2023/4/18, Tue.)(https://www.theguardian.com/world/2023/apr/19/russia-ukraine-war-at-a-glance-what-we-know-on-day-420-of-the-invasion(https://www.theguardian.com/world/2023/apr/19/russia-ukraine-war-at-a-glance-what-we-know-on-day-420-of-the-invasion))
Ukraine’s government has criticised Luiz Inácio Lula da Silva for his efforts to broker a peace deal between Kyiv and Moscow, and invited the Brazilian leader to visit the war-torn country and see for himself the consequences of the Russian invasion. Lula responded by condemning the violation of Ukraine’s territorial integrity by Russia and again called for mediation to end the war.
The G7 has criticised Russia’s threat to station nuclear weapons in Belarus, promising to intensify sanctions on Moscow for its war on neighbouring Ukraine. Belarusian president Alexander Lukashenko held a meeting with the Russian-installed head of Ukraine’s Donetsk region on Tuesday, the state-run Belta news agency reported.
*
Poland has said that it has reached an agreement on restarting transit of Ukrainian grains through its territory as of Friday, according to Polish Agriculture Minister Robert Telus.
Poland also announced plans to install thousands of cameras and motion sensors along its border with Russia’s Kaliningrad enclave to prevent what Warsaw says are illegal migrant crossings orchestrated by Moscow. Polish interior minister Mariusz Kaminski said the system would join a barbed wire fence being built on the 200-kilometre frontier.
*
Security concerns have prompted Russian authorities this year to cancel traditional nationwide victory day processions where people carry portraits of relatives who fought against Nazi Germany in the second world war, a lawmaker said on Tuesday.
Russia is “not yet” planning to block Wikipedia, its minister of digital affairs said on Tuesday as a Moscow court handed the online encyclopedia another fine for failing to remove content Russia deems illegal.
- Pjotr Sauer, “Wagner mercenary admits ‘tossing grenades’ at injured Ukrainian PoWs”(2023/4/18, Tue.)(https://www.theguardian.com/world/2023/apr/18/wagner-mercenary-admits-tossing-grenades-at-injured-ukrainian-pows(https://www.theguardian.com/world/2023/apr/18/wagner-mercenary-admits-tossing-grenades-at-injured-ukrainian-pows))
Aformer Wagner mercenary has admitted to killing and torturing dozens of Ukrainian prisoners of war, in one of the most detailed first-person accounts of atrocities committed by Russian forces in Ukraine.
Alexey Savichev, 49, a former Russian convict recruited by Wagner last September, told the Guardian in a telephone interview that he participated in summary executions of Ukrainian prisoners of war during his six months of fighting in eastern Ukraine.
“We were told not to take any prisoners, and just shoot them on the spot,” he said.
In one instance, while fighting near the eastern Ukrainian city of Soledar last autumn, Savichev said he participated in the killings of 20 Ukrainian soldiers who were surrounded. “We sprayed them with our bullets,” he said. “It is war and I do not regret a single thing I did there. If I could, I would go back.”
Savichev said that in another episode, with other Wagner fighters he had killed “several dozen” injured Ukrainian PoWs by “tossing grenades” into the ditch where they were held near the city Bakhmut in January. “We would torture soldiers too, there weren’t any rules,” he said.
Savichev’s account was first published on Monday by the [Gulagu.net](http://gulagu.net/) rights group in an hour an 17 minute-long video, where he appeared alongside another former Wagner fighter, identified as Azamat Uldarov, who also said he had killed civilians, including children, during the battle for Bakhmut.
Uldarov said his fellow mercenaries in one instance killed a group of people who had taken shelter in the basement of a nine-floor block of flats in Bakhmut, including a young girl. “She was screaming, she was a little kid, she was five or six and I shot her, a kill shot. I wasn’t allowed to let anyone out, you understand?” Uldarov told Vladimir Osechkin, the head of the [Gulagu.net](http://gulagu.net/) rights group. He could not be reached for comment.
The Guardian cannot independently verify either man’s harrowing claim but has seen Russian penal documents showing that Savichev, who was a convicted murderer, was released from a prison in Voronezh, a city in south-west Russia, on a presidential pardon on 12 September.
Wagner has recruited tens of thousands of inmates, including convicted murderers, to fight in eastern Ukraine. They were offered freedom if they survived a near-suicidal six-month stint, one Savichev completed on 12 March.
- Verna Yu, “How one man went from China’s Communist party golden child to enemy of the state”(2023/4/17, Mon.)(https://www.theguardian.com/global-development/2023/apr/17/how-one-man-went-from-chinas-communist-party-golden-child-to-enemy-of-the-state(https://www.theguardian.com/global-development/2023/apr/17/how-one-man-went-from-chinas-communist-party-golden-child-to-enemy-of-the-state))
The 50-year-old human rights lawyer and champion of social equality was sentenced to 14 years in jail earlier this month, along with fellow activist and lawyer Ding Jiaxi, who was jailed for 12 years. Both were convicted of the crime of “subversion of state power.”
The Communist party-controlled court has accused Xu of intending to overthrow the current regime by promoting his vision of “a beautiful China.” According to a court indictment, with a series of articles, blogs, websites and secret meetings, Xu, Ding and other activists were “seriously endangering national security and social stability.”
But the government once felt very differently about Xu, and experts say Xu’s dramatic life symbolises the rise and fall of China’s ill-fated rights movement.
Twenty years ago, Xu was a golden boy feted by the Chinese government and the state media. Along with fellow PhD law graduates Teng Biao and Yu Jiang, he successfully lobbied the national legislature to abolish rules on detaining and repatriating migrants after a young man was beaten to death in custody. The trio were hailed by the Ministry of Justice and state broadcaster CCTV as “the top ten legal figures of 2003.”
The “Sun Zhigang incident” in 2003, named after the young man who died, marked the beginning of China’s rights defence movement.
In the following years, Xu and Teng made it their mission to seek justice for the underprivileged. They and other lawyers set up the Open Constitution Institute, a non-profit legal aid centre, to provide free legal advice for people with grievances. Xu also campaigned for children of migrant workers’ education rights, investigated extralegal “black jails” which locked up petitioners and wrote research reports on social issues. He was showered with awards by the state media, and was named one of “Ten most outstanding young leaders” by a state-run magazine in 2006.
But as Xu’s popularity grew, the authorities became increasingly wary. In 2009 the authorities closed Open Constitution Institute, accusing it of tax evasion. Xu, a lecturer, was taken into custody and barred from teaching.
Upon his release in 2009, he said in an interview that his vision remained unchanged: “I dream of a country that has democracy, rule of law, equality, and justice … a simple and happy society.”
In the following years, Xu set up the social campaign New Citizens Movement, a loose network of activists who met regularly to discuss rights issues and the country’s future. When Xi Jinping came to power in late 2012, Xu wrote an open letter, challenging him to implement constitutional democracy. Around then, the police stepped up their surveillance on him, frequently detaining him or putting him under house arrest .
*
After staging protests for equal rights for migrant children and demanding official transparency over private assets, Xu was arrested in July 2013 and jailed in January 2014 for “assembling a crowd to disrupt order in a public place.” He wept when his lawyer showed him a picture of his baby daughter, born two weeks before the sentencing.
Even after his release in 2017, he insisted on pushing his civil society initiatives – efforts that the court indictment called “subverting state power through advocating non-violent ‘colour revolution’.” After a gathering of about 20 lawyers and activists in Fujian province in December 2019, the authorities arrested more than half of the participants, including Ding. While hiding, Xu published an essay to urge Xi to resign over the coronavirus crisis and the Hong Kong pro-democracy protests. He was arrested in Guangzhou in February 2020 and along with Ding, were tried in June 2022 for “subversion of state power.”
- Simon Tisdall, “When Macron met Xi: welcome to the new world disorder”(2023/4/16, Sun.)(https://www.theguardian.com/world/2023/apr/16/when-emmanuel-macron-met-xi-jinping-new-world-disorder(https://www.theguardian.com/world/2023/apr/16/when-emmanuel-macron-met-xi-jinping-new-world-disorder))

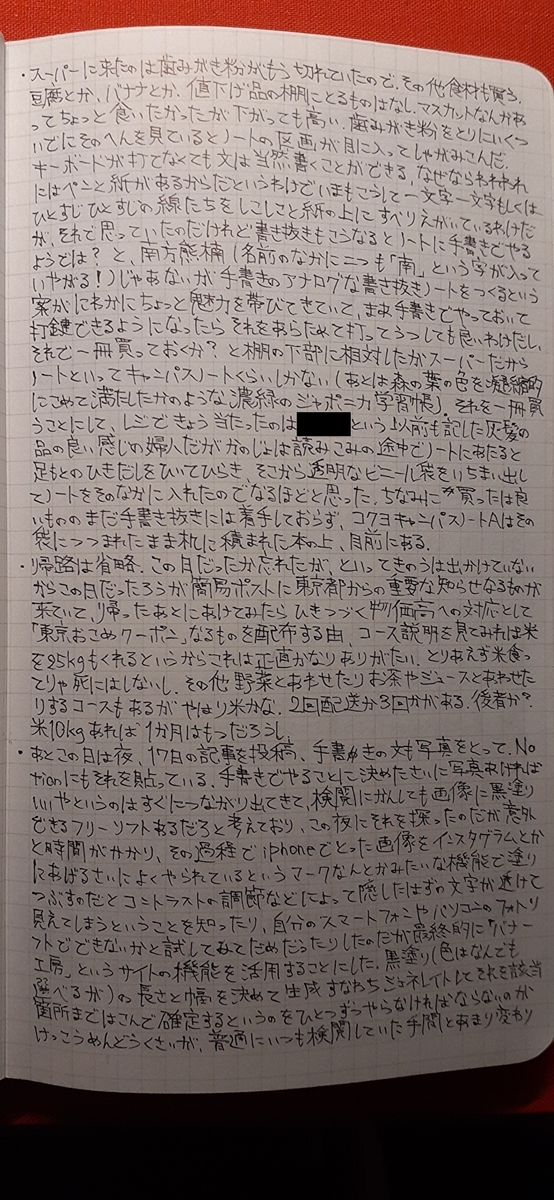

―――――
- 日記読み: 2022/4/19, Tue.
- 「読みかえし2」: 1381 - 1397
- 「ことば」: 1 - 3
2023/4/18, Tue.
一九二九年の特別暑い日のこと、三人の青年がメディネット・マディからほど遠からぬ、なかば砂に埋もれた廃墟を通りかかり、丸屋根の下にぼろぼろに朽ちた木の箱を発見した。箱は太陽の光にさらされて瞬時に崩れ去り、その中から腐朽したパピルスの束がいくつか姿を現した。水が紙の奥深くまで浸透していたため、数え切れぬほど多くの世代にわたって虫や蟻の被害は免れたものの、代わりに非常に細かい塩の結晶に蝕まれていた。青年たちはすぐにそれらの本を手に古物商のもとを訪れたが、この縁が黒く変色した紙の塊のために金を出すことを最初はためらった。後にその朽ちた束の一つを鑑定した修復士もまた、果たしてそこから太古の秘密を引き出せる時が来るかと訝しんだ。
彼はようやく何か月もかかって、くしゃみをしただけですぐに粉々になってしまいそうに薄くて破れやすい本の頁を、斜めに置いた台板とごく小さなピンセットの助けを借りて、一枚ずつばらばらに剝がすことに成功した。それは偶然か、それとも神意か! ベルリンで古文書学者たちが拡大鏡と鏡(end167)を手に、ガラス板の下に広げてのばした、絹のように光る聖典とおぼしき書物の断片をのぞき込んでいた頃、物理学者フリッツ・ツヴィッキーはロサンゼルスからほど遠からぬ山上にあるカリフォルニアの天文台で、直径二百インチの反射望遠鏡をかみのけ座の方向へ向けた。そしていくつものぼんやりした星雲、それらは独立した銀河であることが明らかにされていくのだが、そうした星雲の動きを観察し、自分の計算と比較するうちに、彼はあることを発見するに至る。
目に見える物質だけでは、この銀河団を束ねておくには力が足りない。宇宙には目に見えない物質が存在するに違いなく、その存在はそこから生じる重力によってのみ認識しうる。これこそ他の物質にほんの少しだけ先んじて凝集し始める物質で、その重力が残した痕跡に、他のあらゆる物質は従わざるをえない。神秘的な力、新たな宇宙の勢力、それをツヴィッキーはその未知の性質ゆえに「暗黒物質 [ダーク・マター] 」と呼んだ。
ベルリンの古文書学者たちはその間、ガラスで守られた断片を並べ替え、見事に書かれた文字を解読し始めた。断片はマニの信徒の滅亡を予言し、彼らに加えられることになる残虐な仕打ちを詳細に描写していた。しかし、それはまたこんなことをも告げていた。幾千もの書物が救われるであろう。それらは心の正しき者ら、敬虔なる者らの手に渡るであろう。大福音書と生命の宝、プラグマテイアと秘儀の書、巨人の書と書簡、わが主に捧げる賛歌と祈祷文、絵本と啓示、寓話と密儀――一つとして失われる物はないであろう。どれほど多くが失われ、破滅するだろうか。幾千冊かが失われ、幾千冊かが彼らの手に託される、そうして彼らはふたたび私の書を見出すであろう。彼らはそれに接吻して言うであろう。「おお、偉大なる者らの智慧よ! 光の使徒の鎧よ! おまえはどこに迷い込んでいたのか。どこから来たのか。おまえはどこで見つけられたのか。この書がわれらのもとに届けられたことに、私は歓声をあげる」(end168)人々がそれらの書物を声に出して読み、一つ一つの書の名を告げ、主の名と、それを書くためにすべてを抛った者らの名、そしてそれを書き留めた者の名、句読点を記した者の名を呼ぶのを、おまえは目にするであろう。
(ユーディット・シャランスキー/細井直子訳『失われたいくつかの物の目録』(河出書房新社、二〇二〇年)、167~169; 「マニの七経典」; 結び)
- (……)さんのブログよりもろもろ。
忘我において体験されるものは(それが何であるかについて語ることがまったくのところ許されるなら)、我の一体性である。しかし一なるものとして体験されるためには、我は一なるものになっていたのでなくてはならない。完全に一体化されていた者だけが一体であるものを受けいれることができるのである。そのときこの人間はもはやさまざまなものを集めた束ではなくて、ひとつの火である。彼の経験の内容、彼の経験の主体が、また世界と我とが合流してしまっているのである。このときにはあらゆる力が共振してひとつの力になり、あらゆる火花が燃えつどってひとつの炎になるのである。このとき彼は営為から遠ざかってこのうえなく静か、このうえなく無言語的な天上の国に委ねられ、営為がかつてその伝達に仕えるはしためとするために骨折ってつくりだした言語からも――また、およそ生命を得てよりこのかた永遠にわたって、一なるもの、不可能なるものを希求している言語、営為のうなじに足をすえてまったく真理に、純粋性に、詩になろうとするそのような言語からも脱却しているのである。
(マルティン・ブーバー/田口義弘・訳『忘我の告白』より「忘我と告白」)*
私たちは私たちの内部へと耳をすまし――そうしながら知らないのだ、どの海のさわだちを私たちが聴いているのかを。
(マルティン・ブーバー/田口義弘・訳『忘我の告白』より「忘我と告白」)*
ちなみに大学に入学して最初に書かされた(日本語の)小論文はじぶんの知るかぎりクラスメイトの中で最低点だった(いくら勉強にやる気がなかったとはいえこれはちょっと恥ずかしいと思ってひとの目にふれないように隠した記憶があるからたぶん間違いない)。そんなやつでもまあ時間さえかければそこそこの文章を読み書きできるようになるものなのだ。小説家にでもなってひとやまあてるかと志しはじめたばかりのころはコンプレックスのように思えて仕方なかった思春期を文学どころかあらゆる芸術と無縁に無為に無駄に過ごしてしまったこの経歴が、じつをいうとかなりの武器にもなりうるんでないかと最近はときどき思う。というか以前よりときどき思っていたその論理にわずかながら実感がともないはじめたというべきかもしれない。ハイカルチャーにもサブカルチャーにもひとしくごくごく一般的な興味と無関心を保ちながら芸術の外で営まれる生活を地方のヤンキー文化にどっぷり疑問のかけらもなく染め抜かれながら過ごしていたドアホにしか見ることのできぬ光景もあるだろうし、そのドアホが都会に出ていきなり芸術にかぶれてしまったこの変身の衝撃にだってほかのだれでもない自分自身がいちばん今だって驚いているし、多くの作家がインタビューで問われることになる思春期をともに過ごした一冊がマジでないというか本といえば中高通して週刊少年ジャンプとグラップラー刃牙しか読んでいなかったわかりやすいドアホがさながら交通事故で頭を打ったとたんに絵心にめざめた多くのアウトサイダーたちと軌を一にするかのごとく辿りはじめたあの遅刻者だけが目にすることのできる無人の道のりのしずけさなんてたぶんほとんどのひとが知らない。じぶんには遅刻するという特権が与えられた。物心ついたときからそばにあって常にじぶんをなぐさめはげましてくれるものとしての文学を知らずにいることができた。これが強みになりうることの確信にいま、具体的な実感がともないはじめている。
*
それから、この日の記事の末尾には「これ、すごすぎるな。こういうのがヒーローっていうんだよ」というコメントとともに、毎日新聞の記事へのリンクがはられていたのだが、当然そのリンクは10年後のいま失効している。それでURLを検索してみたところ、全文引いている個人ブログが見つかった。すばらしい内容だったので、ここにも記録しておく。「追悼・三國連太郎さん:徴兵忌避の信念を貫いた(特集ワイド「この人と」1999年8月掲載)」というタイトル。
徴兵を忌避して逃げたものの、見つかって連れ戻され、中国戦線へ。しかし人は殺したくない。知恵を絞って前線から遠のき、一発も銃を撃つことなく帰ってきた兵士がいる。俳優・三國連太郎さんは、息苦しかったあの時代でも、ひょうひょうと己を貫いた。終戦記念日を前に、戦中戦後を振り返ってもらった。【山本紀子】
−−とにかく軍隊に入るのがいやだったんですね。
▼暴力や人の勇気が生理的に嫌いでした。子供のころ、けんかしてよく殴られたが、仕返ししようとは思わない。競争するのもいや。旧制中学で入っていた柔道部や水泳部でも、練習では強いのに、本番となると震えがきてしまう。全く試合にならない。それから選抜競技に出るのをやめました。
−−どうやって徴兵忌避を?
▼徴兵検査を受けさせられ、甲種合格になってしまった。入隊通知がきて「どうしよう」と悩みました。中学校の時に、家出して朝鮮半島から中国大陸に渡って、駅弁売りなどをしながら生きていたことがある。「外地にいけばなんとかなる」と思って、九州の港に向かったのです。ところが途中で、実家に出した手紙があだとなって捕まってしまったのです。
「心配しているかもしれませんが、自分は無事です」という文面です。岡山あたりで出したと思う。たぶん投かんスタンプから居場所がわかったのでしょう。佐賀県の唐津で特高らしき人に尾行され、つれ戻されてしまいました。
−−家族が通報した、ということでしょうか。
▼母あての手紙でした。でも母を責める気にはなれません。徴兵忌避をした家は、ひどく白い目で見られる。村八分にされる。おそらく、逃げている当事者よりつらいはず。たとえいやでも、我が子を送り出さざるを得なかった。戦中の女はつらかったと思います。
◇牢に入れられるより、人を殺すのがいやだった
−−兵役を逃れると「非国民」とされ、どんな罰があるかわからない。大変な決意でしたね。
▼徴兵を逃れ、牢獄(ろうごく)に入れられても、いつか出てこられるだろうと思っていました。それよりも、鉄砲を撃ってかかわりのない人を殺すのがいやでした。もともと楽観的ではあるけれど、(徴兵忌避を)平然とやってしまったのですね。人を殺せば自分も殺されるという恐怖感があった。
−−いやいや入ったという軍隊生活はどうでした?
▼よく殴られました。突然、非常呼集がかかって、背の高い順から並ばされる。ところが僕は動作が遅くて、いつも遅れてしまう。殴られすぎてじきに快感になるくらい。演習に出ると、鉄砲をかついで行軍します。勇ましい歌を絶唱しながら駆け足したり、それはいやなものです。背が高いので大きな砲身をかつがされました。腰が痛くなってしまって。そこで仮病を装ったんです。
−−どんなふうに?
▼毛布で体温計の水銀の部分をこすると、温度が上がるでしょう。38度ぐらいまでになる。当時、医者が足りなくて前線には獣医が勤務していました。だからだまされてしまう。療養の命令をもらって休んだ。また原隊復帰しなくてはいけない時に、偶然救われたのです。兵たん基地のあった漢口(今の湖北省武漢市)に、アルコール工場を経営している日本人社長がいた。軍に力をもっていたその社長さんが僕を「貸してほしい」と軍に頼んだのです。僕はかつて放浪生活をしていた時、特許局から出ている本を読んで、醸造のための化学式をなぜか暗記していました。軍から出向してその工場に住み込み、1年数カ月の間、手伝いをしていた。そうして終戦になり一発も銃を撃たずにすんだのです。
−−毛布で体温計をこするとは、原始的な方法ですね。
▼もっとすごい人もいました。そのへんを走っているネズミのしっぽをつかまえてぶらぶらさせたかと思うと、食べてしまう。「気が狂っている」と病院に入れられましたが、今ではその人、社長さんですから。
−−前線から逃げるため、死にもの狂いだったのですね。
▼出身中学からいまだに名簿が届きますが、僕に勉強を教えてくれた優しい生徒も戦死していて……。僕は助かった命を大切にしたいと思う。そう考えるのは非国民でしょうか。
−−三國さんのお父様も、軍隊の経験があるそうですね。
▼はい。シベリアに志願して出征しました。うちは代々、棺おけ作りの職人をしていました。でも差別があってそこから抜け出ることができない。別の職業につくには、軍隊に志願しなくてはならない。子供ができて生活を安定させるため、やらざるを得なかったのでしょう。出征した印となる軍人記章を、おやじはなぜだか天井裏に置いていた。小さいころ僕はよく、こっそり取り出してながめていました。
−−なぜ天井裏に置いていたのでしょう。
▼権力に抵抗する人でしたからね。いつだったか下田の家の近くの鉱山で、大規模なストがあって、労働運動のリーダーみたいな人を警察がひっこ抜いていったのです。おやじはつかまりそうな人を倉庫にかくまっていた。おふくろはその人たちのために小さなおむすびを作っていました。またいつだったか、気に入らないことがあったのでしょう、おやじは駐在所の電気を切ったりしていた。頑固で曲がったことの嫌いな人でした。
−−シベリアから帰ってから、どんな職業に?
▼架線工事をする電気職人になりました。お弟子さんもできた。おやじは、太平洋戦争で弟子が出征する時、決して見送らなかった。普通は日の丸を振って、みんなでバンザイするんですが。ぼくの時も、ただ家の中でさよならしただけ。でも「必ず生きて帰ってこい」といっていました。
−−反骨の方ですね。
▼自分になかった学歴を息子につけようと必死でした。僕がいい中学に合格した時はとても喜んでいた。ところが僕が授業をさぼり、家出して、金を作るため、たんすの着物を売り払ったりしたから、すっかり怒ってしまって。ペンチで頭を殴りつけられたり、火バシを太ももに刺されたりしました。今でも傷跡が残っています。15歳ぐらいで勘当され、それから一緒に暮らしたことはありません。
−−終戦後はどんな生活を?
▼食料不足でよく米が盗まれ、復員兵が疑われました。台所まで警察官が入って捜しにくる。一方で、今まで鬼畜米英とみていたアメリカ人にチョコレートをねだっている。みんなころっと変わる。国家というのは虚構のもとに存在するんですね。君が代の君だって、もっと不特定多数の君なのではないか。それを無視して祖国愛を持て、といわれてもね。
−−これからどんな映画を作りたいと思いますか。
▼日本の民族史みたいなものを作りたい。時代は戦中戦後。象徴的なのは沖縄だと思います。でも戦いそのものは描きたくない。その時代を生きた人間をとりまく環境のようなものを描こうと思う。アメリカの戦争映画も見ますが、あれは戦意高揚のためあるような気がします。反戦の旗を振っているようにみえて、勇気を奮い起こそうと呼びかけている。
◇国家とは不条理なものだ
三國さんは名前を表記する時、必ず旧字の「國」を用いる。「国」は王様の「王」の字が使われているのがいやだ、という。「国というものの秘密が、そこにあるような気がして」
「国家というのは、とても不条理なものだと思う」と三國さんはいう。確かにいつも、国にほんろうされてきた。代々続いた身分差別からすべてが始まっている。棺おけ作りの職業にとめおかれていた父親は、全く本意ではなかったろうが、シベリア出兵に志願して国のために戦った。そうして初めて、違う職業につくことを許された。この父との確執が、三國さんの人生を方向づけていく。
学歴で苦労した父は、息子がいい学校に入ることを望んだ。しかし期待の長男・連太郎さんは地元の名門中学に合格したまではよかったが、すぐドロップアウトしていく。三國さんは「優秀な家庭の優秀な子供がいて、その中に交じっているのがいやだった。自信がなかった」という。
時代も悪かった。中学には配属将校といわれる職業軍人がいた。ゲートルを巻いての登校を義務づけられ、軍事教練もあった。
学校も家も息苦しい。だから家出した。中学2年のことだ。東京で、デパートの売り子と仲良くなって泊めてもらったこともある。中学は中退してしまう。父は激怒した。中国の放浪から帰ってきた時、勘当された。家の近くのほら穴で「物もらいと一緒に寝起きした」という。道ですれ違おうものなら、父は鬼のような形相で追いかけてきた。
その後、三國さんが試みた徴兵忌避は、不条理な国に対する最大の抵抗だった。後ろめたさはない。圧倒的多数が軍国主義に巻き込まれていく中、染まらずにすんだのは、「殺したくない」という素朴な願いを持ち続けたためである。
「国とは何なのか、死ぬまでに認識したい。今はまだわからないが、いつもそれを頭に置いて芝居を作っている」と三國さんは話している。
- John Fordham, “Ahmad Jamal obituary”(2023/4/17, Mon.)(https://www.theguardian.com/music/2023/apr/17/ahmad-jamal-obituary(https://www.theguardian.com/music/2023/apr/17/ahmad-jamal-obituary))。Ahmad Jamal死去。御大がRed GarlandにJamalみたいにやれといったのはゆうめいなはなしだけれど、Philly Joe Jonesのリムショットのほうは知らなかった。
Jamal was born Frederick Jones in Pittsburgh, Pennsylvania, and regarded the eclectic musical culture of his birthplace as crucial to his development. His father was an open-hearth worker in the steel mills, but his uncle Lawrence played the piano and at only three years old Jamal was copying his playing by ear. He took lessons from seven, and would recall “studying Mozart along with Art Tatum”, unaware of white society’s widespread prejudice that European music was supposed to be superior to that of African-Americans. Significant influences in his early years were the music teacher Mary Cardwell Dawson (founder of the National Negro Opera Company), and his aunt Louise, who showered him with sheet music for the popular songs of the day. Pianists Tatum, Nat King Cole and Erroll Garner were among the young “Fritz” Jones’s principal jazz influences, and he also studied piano with James Miller at Westinghouse high school.
At 17 he toured with the former Westinghouse student George Hudson’s Count Basie-influenced orchestra, worked in a song-and-dance team, and wrote one of his most enduring themes, Ahmad’s Blues, at 18. Two years later he adopted Islam, and the name Ahmad Jamal. He also joined a group called the Four Strings, which became the Three Strings with the departure of its violinist, and caught the ear of the talent-spotting producer John Hammond, who signed the trio to Columbia’s Okeh label.
The public liked Jamal’s distinctive treatments of popular songs, and so did Davis. Developing his new quintet in 1955, Davis sent his rhythm section to study Jamal’s then drummerless group. Davis liked Jamal’s pacing and use of space (the prevailing bebop jazz style was usually hyperactive), and he noticed that Jamal’s guitarist, Ray Crawford, often tapped the body of his instrument on the fourth beat. Davis told his drummer, Philly Joe Jones, to copy the effect with a fourth-beat rimshot, which became a characteristic sound of that ultra-hip Davis ensemble. Davis began to feature Jamal’s originals and arrangements in his own output, including New Rhumba (on his 1957 Miles Ahead collaboration with Gil Evans), and Billy Boy (on 1958’s classic Milestones session).


2023/4/17, Mon.
やがて殉教の時が近づくと、マニは弟子たちに言った。「私の本を大切にしなさい! そして折に触れて私が口にした智慧の言葉も、失われぬうちに書き留めておくように」
それらは赤々と燃えた。それらを食いつくす炎の中から、純金が流れ出した。だが、マニ教の聖なる書物をのみ込んだのは世界の業火でも、燃えさかる宇宙でもなく、彼らの敵が築いた火炙り用の薪の山だった。いかなる反論も許されず、疑いを口にすれば必ず罰せられた。なぜなら神を信ずる者ある所、神を知らざる者あり、敬虔なる信徒ある所、邪宗徒あり。ちょうどマニが光と闇を峻別したように、真の教えがある所には、正と誤を厳格に区別しようとする忠実な信者の熱狂があっという間に燃え広がった。炎は偽りのみを焼きつくすとはいうが、火はやはり選り好みはしないものだ。
この時、マニ教の聖典とともに燃やされたものは何か。世界の滅亡の計算書、大量の魔法書、悪魔を呼び出す呪術書、存在についての無数の相対立する哲学書、何千部ものユダヤ教の経典 [タルムード] 、オウィディウスの作品全集、さまざまな論文、聖三位一体と魂の不滅性について、万象の無限性と宇宙の本当の大きさについて、この世の形と天体の配置に占めるその位置について。審問は何日もつづき、薪の山は何世紀も燃えつづけた。その火は全知を気どる者らの心をあたため、アレクサンドリアとコンスタンチノープルとローマの風呂を沸かした。もはや目が理性を欺き得なくなり、自然が書物を教え導くようになるまで。真実がどれほど巨大であれば、周りを取り囲むすべての誤謬の闇をかき消し、世界を真実の光で満たすことができるのだろう。遠くにある物を怖いほど近くに引き寄せる新しい望遠鏡が作られるたびに、限界は押し上げられ、視野は広がる。空に浮かぶ皿は軌道になり、円は楕円(end165)になり、濃淡の霧は球状星団と渦巻星雲と銀河になり、六つだと思われていた惑星は七つ、八つ、九つ、そしてまた八つになり、宗教的秘儀は物質になる――その成立過程はマニの宇宙論に劣らず奇抜なものだ――惑星を軌道上に保つ恒星、星を引き寄せのみ込むブラックホール、遠い未来へもうだれも受け取る者のない光を放射する霧。どれほど多くの数字や公式が宇宙を表そうと、どのような知見が宇宙の本質に迫ろうと同じことだ。時がつづくかぎり――それを疑う者がいるだろうか――どんな説明も所詮は物語にすぎない。引力と斥力、初めと終わり、生成と消滅、偶然と必然についてのお馴染みの物語。宇宙は成長し、膨張し、銀河と銀河を引き離し、まるでそれを把握しようとする理論をかわして逃れようとするかに見える。この逃げゆく宇宙、不安定な空虚の中へ増殖していく宇宙という考えの方が、収縮という考え、縮んで元の小さな脆弱な点に戻るという考えよりも不気味に思われる。その小さな点、すべての力と質量、すべての時間とすべての空間が渾然一体となり、ひと塊になっていた点から、かつてすべてが始まったのだ。最初は点、つづいて塊、生き埋めの。そして爆発、膨れあがっていく空間、高温で高密度に圧縮された状態、そこから膨張し、冷却し、その中から原子が生まれ、光と物質が分かれて、目に見える世界を形作っていく――恒星、分子の雲、塵、宇宙の虫けら。始まりを問うことは、終わりを問うこと。すべてが拡張し、加速し、ある日反転してふたたび収縮する。誕生も崩壊も知らない循環の中に閉じ込められて。私たちが知っていることはどれだけあるのだろう! ただこれだけはほぼ確実だ。世界の終わりが来るということ。それは一時的な終わりかもしれないが、想像しうるもっとも恐ろしい終末であることに変わりはない。太陽が巨大に膨れあがり、水星と金星をのみ込み、地球の空はすべて太陽に覆われる。すさまじい高温の熱が海水をすべて蒸発させ、岩石を溶かし、地殻を引き剝がし、地球の最深部を外へ引きずり出すだろう。やがて冷気が流れ込み、時は終わる。
(ユーディット・シャランスキー/細井直子訳『失われたいくつかの物の目録』(河出書房新社、二〇二〇年)、165~166; 「マニの七経典」)
- 一年前。「あと、となりの(……)さんが今朝だかきのうの四時に亡くなったらしい。一〇一歳だか一〇二歳だかわすれたが、いずれにしても大往生。とつぜんくるしいようすになってそのままながびきもせずに逝ったと。さいごまでたいしたものだった」とのこと。
- 風景。
四時ごろにはやめに上階にあがってアイロン掛け。手をうごかしながらときおり顔をあげて、正面、南窓のむこうをみやる。風景に春の葉の量が増えてその範囲がひろくなり、空間がいかにもみどりして、陽のいろのない平板な空気ながら色調があかるくいろどられているのがみてとれる。空はかわらずのとざされた白曇りで、やまぎわちかくにはほんのわずかな窪みといったかんじで青灰色がほのかに混ざりながれており、そのしたの山は冬も生きていた濃緑よりも、いつのまにかはだかをやめた木の若い明緑がおおいくらいで、巨人がそこをのぼるためのみちびきのように斜面をいろどり染めている。
- この日青空文庫で樋口一葉をすこしずつ読んでいこうとおもって、あいうえお順でいちばんうえに来ている「あきあはせ」というやつをまず読んだのだが、これがよかった。小説というより随筆もしくは随想だが。したにぜんぶ引いてしまう。ルビのいるものいらないものを選別していちいちカッコ内におさめていくのがめんどうくさかった。
雨の夜
庭の芭蕉 [ばせを] のいと高やかに延びて、葉は垣根の上やがて五尺もこえつべし。今歳 [ことし] はいかなれば、かくいつまでも丈のひくきなど言ひてしを、夏の末つかた極めて暑かりしに唯一日 [ひとひ] ふつか、三日とも数へずして驚くばかりになりぬ。秋あきかぜ少しそよ/\とすれば、端のかたより果敢 [はか] なげに破れて、風情次第に淋しくなるほど、雨の夜の音なひこれこそは哀れなれ。こまかき雨ははら/\と音して草村がくれ鳴 [なく] こほろぎのふしをも乱さず、風一しきり颯 [さつ] と降 [ふり] くるは、あの葉にばかり懸るかといたまし。
雨は何時も哀れなる中に秋はまして身にしむこと多かり。更けゆくまゝに燈火 [ともしび] のかげなどうら淋しく、寝られぬ夜なれば臥床 [ふしど] に入らんも詮なしとて、小切れ入れたる畳紙 [たたうがみ] とり出だし、何とはなしに針をも取られぬ。まだ幼 [いとけ] なくて伯母なる人に縫物ならひつる頃、衽先 [おくみさき] 、褄 [つま] の形 [なり] など六づかしう言はれし。いと恥かしうて、これ習ひ得ざらんほどはと、家に近き某 [それ] の社 [やしろ] に日参 [につさん] といふ事をなしける、思へばそれも昔しなりけり。をしへし人は苔の下になりて、習ひとりし身は大方もの忘れしつ。かくたまさかに取出るにも指の先こわきやうにて、はか/″\しうは得も縫ひがたきを、かの人あらばいかばかり言ふ甲斐なく浅ましと思ふらん、など打返しそのむかしの恋しうて、無端 [そゞろ] に袖もぬれそふ心地す。
遠くより音して歩み来るやうなる雨、近き板戸に打つけの騒がしさ、いづれも淋しからぬかは。老たる親の痩せたる肩もむとて、骨の手に当りたるも、かかる夜はいとゞ心細さのやるかたなし。
月の夜
村雲 [むらくも] すこし有るもよし、無きもよし。みがき立てたるやうの月のかげに尺八の音 [ね] の聞えたる、上手ならばいとをかしかるべし。三味 [さみ] も同じこと、琴は西片町 [にしかたまち] あたりの垣根ごしに聞たるが、いと良き月に弾く人のかげも見まほしく、物がたりめきて床しかりし。親しき友に別れたる頃の月、いとなぐさめがたうもあるかな。千里 [ちさと] のほかまでと思ひやるに、添ひても行 [ゆか] れぬ物なれば唯うらやましうて、これを仮に鏡となしたらば、人のかげも映るべしやなど、果敢なき事さへ思ひ出でらる。
さゝやかなる庭の池水 [いけみづ] にゆられて見ゆるかげ物いふやうにて、手すりめきたる所に寄りて久しう見入るれば、はじめは浮きたるやうなりしも次第に底ふかく、この池の深さいくばくとも量 [はか] られぬ心地になりて、月はそのそこの底のいと深くに住らん物のやうに思はれぬ。久しうありて仰ぎ見るに、空なる月と水のかげと孰 [いづ] れを誠 [まこと] のかたちとも思はれず。物ぐるほしけれど箱庭に作りたる石一つ水の面にそと取落せば、さゞ波すこし分れて、これにぞ月のかげ漂ひぬ。かくはかなき事して見せつれば、甥なる子の小さきが真似て、姉 [あね] さまのする事我われも為すとて、硯の石いつのほどに持て出でつらん、我れもお月さま砕くのなりとて、はたと捨てつ。それは亡き兄の物なりしを身に伝へていと大事と思ひたりしに、果敢なき事にて失なひつる罪得がましき事とおもふ。この池かへさせてなど言へども、まださながらにてなん。明ぬれば月は空に帰りて余波 [なごり] もとゞめぬを、硯はいかさまになりぬらん、夜よな/\影や待 [まち] とるらんと哀なり。
嬉しきは月の夜の客人 [まれびと] 、つねは疎々しくなどある人の心安げに訪 [と] ひ寄たる。男にても嬉しきを、まして女の友にさる人あらば、いかばかり嬉しからん。みづから出 [いづ] るに難 [かた] からば文 [ふみ] にてもおこせかし。歌よみがましきは憎くき物なれど、かかる夜の一ト言には身にしみて思ふ友ともなりぬべし。大路 [おほぢ] ゆく辻占 [つじうら] うりのこゑ、汽車の笛の遠くひゞきたるも、何なにとはなしに魂あくがるゝ心地す。
雁がね
朝月夜 [あさづくよ] のかげ空に残りて、見し夢の余波もまだ現なきやうなるに、雨戸あけさして打ながむれば、さと吹く風竹の葉の露を払ひて、そゞろ寒けく身にしみ渡る折しも、落 [おち] くるやうに雁がねの聞えたる、孤 [ひと] つなるは猶さら、連ねし姿もあはれなり。思ふ人を遠き県 [あがた] などにやりて、明くれ便りの待わたらるゝ頃、これを聞たらばいかなる思ひやすらんと哀れなり。朝霧ゆふ霧のまぎれに、声のみ洩らして過ぎゆくもをかしく、更けたる枕に鐘の音 [ね] きこえて、月すむ田面 [たのも] に落 [おつ] らんかげ思ひやるも哀れ深しや。旅寐の床、侘人 [わびびと] の住家 [すみか] 、いづれに聞 [きき] ても物おもひ添ふる種なるべし。
一 [ひと] とせ下谷 [したや] のほとりに仮初 [かりそめ] の家居 [いへゐ] して、商人 [あきびと] といふ名も恥かしき、唯いさゝかの物とり並べて朝夕のたつきとせし頃、軒端 [のきば] の庇あれたれども、月さすたよりとなるにはあらで、向ひの家の二階のはづれを僅かにもれ出 [いづ] る影したはしく、大路に立 [たち] て心ぼそく打あふぐに、秋風たかく吹きて空にはいさゝかの雲もなし。あはれかかる夜よ、歌よむ友のたれかれ集ひて、静かに浮世の外 [ほか] の物がたりなど言ひ交はしつるはと、俄かにそのわたり恋しう涙ぐまるゝに、友に別れし雁唯一つ、空に声して何処 [いづこ] にかゆく。さびしとは世のつね、命つれなくさへ思はれぬ。擣衣 [きぬた] の音 [おと] に交りて聞えたるいかならん。三つ口など囃して小さき子の大路を走れるは、さも淋しき物のをかしう聞ゆるやと浦山しくなん。
虫の声
垣根の朝顔やう/\小さく咲きて、昨日今日葉がくれに一花 [ひとはな] みゆるも、そのはじめの事おもはれて哀れなるに、松虫すゞ虫いつしか鳴 [なき] よわりて、朝日まちとりて竈馬 [こほろぎ] の果敢なげに声する、小溝の端、壁の中など有るか無きかの命のほど、老たる人、病める身などにて聞たらば、さこそ比らべられて物がなしからん。まだ初霜は置くまじきを、今年は虫の齢ひいと短かくて、はやくに声のかれ/″\になりしかな。くつわ虫はかしましき声もかたちもいと丈夫めかしきを、何 [いつ] しか時の間におとろへ行くらん。人にもさる類ひはありけりとをかし。鈴虫はふり出 [いで] てなく声のうつくしければ、物ねたみされて齢ひの短かきなめりと点頭 [うなづ] かる。松虫も同じことなれど、名と実と伴はねばあやしまるゝぞかし。常盤 [ときは] の松を名に呼べれば、千歳 [ちとせ] ならずとも枯野の末まではあるべきを、萩 [はぎ] の花ちりこぼるゝやがて声せずなり行く。さる盛りの短かきものなれば、暫時 [しばし] も似 [あへ] よとこの名は負 [おは] せけん、名づけ親ぞ知らまほしき。
この虫一とせ籠 [こ] に飼ひて、露にも霜にも当てじといたはりしが、その頃病ひに臥したりし兄の、夜な/\鳴くこゑ耳につきて物侘しく厭はしく、あの声なくは、この夜やすく睡らるべしなど言へるも道理 [ことわり] にて、いそぎ取おろして庭草の茂みに放ちぬ。その夜なくやと試みたれど、さらに声の聞えねば、俄かに露の身に寒 [さぶ] く、鳴くべき勢ひのなくなりしかと憐れみ合ひし、そのとし暮れて兄は空 [むな] しき数に入りつ。又の年の秋、今日ぞこの頃 [ごろ] など思ひ出 [いづ] る折しも、ある夜ふけて近き垣根のうちにさながらの声きこえ出ぬ。よもあらじとは思へど、唯そのものゝやうに懐かしく、恋しきにも珍らしきにも涙のみこぼれて、この虫がやうに、よし異物 [こともの] なりとも声かたち同じかるべき人の、唯今こゝに立出で来たらばいかならん。我れはその袖をつと捉 [と] らへて放つ事をなすまじく、母は嬉しさに物は言はれで涙のみふりこぼし給ふや、父はいかさまに為 [な] し給ふらんなど怪しき事を思ひよる。かくて二夜 [ふたよ] ばかりは鳴きつ。その後 [ご] は何処 [いづこ] にゆきけん、仮にも声の聞えずなりぬ。
今も松虫の声きけばやがてその折おもひ出 [いで] られて物がなしきに、籠に飼ふ事は更にも思ひ寄らず、おのづからの野辺に鳴弱りゆくなど、唯その人の別れのやうに思はるゝぞかし。




2023/4/16, Sun.
そこで彼はまもなく預言者たちの住む洞窟の一つに引きこもると、左脚の上に座り、歩く時に言うことを聞かず、子どもの頃から引きずるしかなかった右脚を前に出して台にした。その上に冊子本を置いて紐をほどき、本を開いて、葦のペンをまっさらの紙に下ろすと、たった一本の補助線も引かずに書き始めた――彼が発明した、あの非の打ちどころのない文字を。優しい繊細な文字、それらは千(end162)年後も、そのうちの残ったものは、肉眼ではほとんど見えなくても、拡大鏡をかざせばくっきりと読めることだろう。
マニはページを繰って、今度は絵筆をパピルスの上に置くと、闇にうごめく生き物たちと世界の創造を描いていった。光の支配者が殺した悪魔の皮を剝ぎ、それを天空に丸く張りめぐらす様子、悪魔の砕けた骨で山を、しなびた肉で大地を造り、あの闘いの時に飛び散った光の粒子から太陽と月を創る様子を。彼はまた、この宇宙を動かし、一つ一つの天体をそれぞれの軌道に乗せたあの神の使者も描いた。それからマニは新しいページを開き、ある衝撃的な真実の全体像を描いていった。光のわずかな残りかすから、最初の男女の人間を神の使者の姿に似せて形作ったのは、闇の支配者であった――互いに合一し、増殖したいという呪われた衝動を彼らに与えたのも。最初の男女、青白い裸の二人はたがいにしがみつき、次々に子どもを作る、それとともに光はますます小さな粒に分かれて散らばり、天国へ帰還できる日はますます遠のいていくのだった。
マニは金箔を小さく切って、その小片をパピルスに貼りつけ、絵の具を何度も塗り重ねた。するとそのページは明るい光を放った。朝になり、夜になった。何日も、何週間も過ぎた。マニは描くのをやめなかった。疲れを知らず回転する巨大な車輪、次第にこの世のすべての光を浄化していく宇宙の車輪、規則正しく満ち欠けする月――煌めくラピスラズリの夜空に浮かぶ黄金色の陶皿――その皿の中に光は集められ、地上の汚れを祓い清められる。そしてほのかに光る渡し舟に乗り、天の川を通って故郷に帰る。誕生の循環から抜け出し、存在をやめることを許された、光の魂。
最後に彼はリスの毛の筆をとり、もう一度神の使者の衣のひだをなぞった。生命の母の眉、太古の人間の金色に輝く甲冑の輪郭、ヤギに似た悪魔の顔も。闇の支配者の髭や、鱗に覆われた足の鉤爪ですら、彼は芸術家の細心さをもって描いた。芸術家は自分の創ったさまざまな形の創造物を等しく愛するが、その愛ゆえに、悪がかつて善であった例しはないこと、悪が善の近縁者でもなければその後(end163)継者でもなく、堕天使でも反逆の巨人でもないこと、その悪さは何によっても説明しえないことを忘れさえする。マニの細密画において、悪は自分自身を嚙み裂く、竜の体と獅子の頭と鷲の翼とクジラの尾を持つ怪物であり、時の始まりから、己の国を荒廃させてきた――熱い灰からもくもくと上がる煙に覆いつくされ、死体の腐敗臭に満ちた戦場の一面に、死んだ木の切り株がごろごろ転がり、深紅に燃える大きな口がぱっくりと開き、その深淵から黄鉛色の煙が立ちのぼっている。マニの教えは白か黒かであっても、彼の写本はうっとりするほど色彩豊かだ。このような本を持つ者は、神殿も教会もいらない。これらの本自体が、内省と智慧と祈りの場だった。豪華な冊子本は分厚い革で装丁された堂々たる本の塊で、薄く削った鼈甲や象牙を優美に埋め込んである。手に馴染む十二折り判は、表紙に金箔を被せ、宝石をちりばめてある。そしてお守りのように極小の本は、拳の中に隠せるくらい小さい。ザクロとランプの煤から作ったインクは、石灰を塗ったパピルスの上でも、白い絹でも、または柔らかい革、ほのかに光る羊皮紙の上でも同じように黒く輝く。ただ本の題名だけが、判読不能なまでに装飾を施されている。けばけばしいバラの花の装飾、臙脂色の点が連なる縁取り。それは救済と破壊の色、世界の炎上の色だった。深紅の光を放つのは、千四百六十八年間燃えつづけた炎。宇宙を燃え上がらせ、その灼熱が最後の光の粒を解放し、世界全体をのみ込んでしまうまで、燃えるのをやめないだろう。そしてひときわ明るく光り輝くのは、壮麗な未来の似姿、白絵の具と金箔で描かれた、あの天上の光の世界だ。そこでは善と悪がふたたび分かれ、闇の元素は、ことごとく下降し、打ち負かされ、沈められ、生き埋めにされる。そして光の元素はすべて高みへ上昇し、月で洗い清められ、天体の回転によって浄化される。信じたい者は、信じるがよい。そして多くの者が信じたがった。
ゾロアスターには無数の弟子がいた。ブッダには五人の同行者、イエスには十二人の使徒が――だが、マニには七冊の経典があった。経典が彼の教えをさまざまな国の言葉で世界へ届けた。あのバベルの塔の建設によって分断されたものを一つにするために、そしてかつて前例のないことだが、彼に(end164)従う者と彼を罵る者とを分裂させるために。人々は彼を善の器マナ、あるいは悪の器と呼んだ。人々は彼を天の糧マンナ、あるいは悪しき者らの阿片と呼んだ。放浪の救世主マニ。足萎えの悪魔マネス。啓示を受け、世界を救済する旅に出た者、マニ。世界を破壊する旅に出た気狂い、マニー――癒し手マニ。災いのマニ。
(ユーディット・シャランスキー/細井直子訳『失われたいくつかの物の目録』(河出書房新社、二〇二〇年)、162~165; 「マニの七経典」)
- 一年前からニュース。
(……)新聞一面はウクライナ情勢。きのうのニュースですでにみたがロシア黒海艦隊の旗艦「モスクワ」沈没の報。大型ミサイル巡洋艦という種類の船であるこの艦は、S300とかいう防空ミサイルをそなえていて、ウクライナ南部に攻撃をしかける隊にたいして防空網を提供する役割をはたしていたといい、したがってそれがうしなわれたのはロシアにとってはおおきな打撃であり海軍力の低下はさけられず、攻撃戦略にも影響があるだろうと。ロシアはキーウにむけてミサイル攻撃を再開し、それは報復の可能性がある。東部への部隊配備はおくれており、総攻撃はまだはじまっていないらしい。ロシアがわはマリウポリの製鉄工場を「解放」したと発表したが、これがきのうおとといにウクライナ軍とアゾフ大隊のさいごの拠点としてつたえられていた製鉄所とおなじものだとすると、マリウポリはいよいよ制圧間近ということになるのではないか。ウクライナがわはその情報を否定。
今年末にむけて自民党が安保関連三文書の要綱案を提案したという報もあった。NATOが各国にもとめている数値にあわせて、GDP比で年二パーセントの防衛費割合を五年以内に実現することをめざすと。いわゆる「敵基地攻撃能力」は専守防衛の枠組みのもとで保有。攻撃対象として基地のみならず敵側の司令本部などもふくむといい、それは司令部をたたかなければミサイル攻撃などの連続をとめることは困難であるとのかんがえからだと。
- 「夕暮れと真昼を分かつ破線上冒険者には既知がみえない」という一首がちょっと良かった。
- Joanna Moorhead and Daisy Schofield, “How to sleep well at any age – from babies (and their parents) to dog-tired midlifers”(2022/12/31, Sat.)(https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2022/dec/31/how-to-sleep-well-health-experts-age-babies-parents(https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2022/dec/31/how-to-sleep-well-health-experts-age-babies-parents))
- Guardian staff and agencies, “Russia-Ukraine war at a glance: what we know on day 417 of the invasion”(2023/4/16, Sun.)(https://www.theguardian.com/world/2023/apr/16/russia-ukraine-war-at-a-glance-what-we-know-on-day-417-of-the-invasion(https://www.theguardian.com/world/2023/apr/16/russia-ukraine-war-at-a-glance-what-we-know-on-day-417-of-the-invasion))
Poland and Hungary have banned imports of grain and other food from Ukraine to protect local farmers, officials from both countries said on Saturday. Ukraine’s grain exports have been transiting through the European Union to other countries since Ukraine’s Black Sea routes were blocked by Russia’s invasion, leading to prices being driven down.
*
The Brazilian president, Luiz Inácio Lula da Silva, has said the US should stop “encouraging war” in Ukraine “and start talking about peace”. In that way, the international community would be able to “convince” the Russian and Ukrainian presidents that “peace is in the interest of the whole world”, Lula told reporters in Beijing at the end of a visit where he met president Xi Jinping.
- いまもう午後一〇時。マジで打鍵すると左手から左半身ぜんたいにかるいしびれのようなきしみがひろがるので、しばらく最低限ですませるしかない。一〇日の夜に実家まであるいたときのしずけさについては書きたかったのでいま記して投稿したが。きょうなんか起きたときから左手の甲がずっとひりついているような始末だった。そしてそれが肘や肩や肩甲骨をとおって腰や膝や足の裏までつうじているのがわかるのだ。しばらく箇条書きの日報形式でがんばるしかない。左手はもともと手首が右にくらべるとわるくて、それは高校時代にすでにそうだったのだが、ギターを弾いているうちに負荷が蓄積されてそうなったのだろう。そうして一〇数年後のいま、若さによってカバーできていたものができないところまで来てしまったようだ。ちなみにいまこれはChromebookのほうで、椅子について膝にのせたそれをあいてに打っており、ふだんつかっているパソコンよりもこっちのほうがキーの感触からしてまだましな気がする。しかしどっちにしてもたいして変わらん。胃液感が出てきたり、首の右側がピクピクしたりするしな。とにかくこれからしばらくのあいだは最低限の箇条書きでがんばりますわ。というかむしろ休んでしまってもよい、むしろそのほうが良いような気もするのだが、まだそこまでの判断はくだせていない。
- きょうのことといって天気は起きたころには曇りだったが昼くらいから雲が割れて青さがのぞき、陽射しもかくされがちではあるもののながれたので洗濯をしたということと、三時くらいにスーパーに買い物に行ったというのと、あとはだいたいごろごろしながら本を読んだり。書きものができないとなると読むかなまけるしか基本やることがない。
―――――
- 日記読み: 2022/4/16, Sat.
- 「読みかえし2」: 1363 - 1381
- 「ことば」: 1 - 3
2023/4/15, Sat.
マニは北へ向けて出発した、ティグリス川左岸の生まれ故郷の街へ。翼のある石の獣に守られた門を通り、集まってくる人々の群れに交ざり、声をあげ、古より預言者たちが語ってきたことを語った。汝らは地の塩なり。この世の光なり。我につづく者は闇を彷徨うことなく、生命の光を得るであろう。
人々は足を止めた。なぜかはわからない。暑さが彼らに一休みするよう促したのかもしれないし、奇妙に斜めに傾いたマニの姿形が人を惹きつけると同時に嫌悪をもよおさせ、通りすがりの者ですら彼とその成長を止めた片脚に目が釘づけになったためかもしれない。しかし、もしかするとそれは彼の伝える言葉のためでもあったかもしれない。彼の言葉の光の中では一切の濃淡が消え、すべてが黒か白になった。魂は善ですでに失われており、物質は悪で堕落している――そして両者の合字である人間は、救済と浄化を切望している。彼の対比の手法が物事を明確に、混じりけのないものにし、現実の世の中を暗く翳らせると同時に、遠い確実な未来を明るく光り輝かせた。その未来とは、いまは失われた、完璧であった原初の時代を再現することに他ならないという。それはめでたき報せに富む土地にもたらされためでたき報せ、福音の乏しからぬ時代の福音、多くの問いへの答えだった。太陽が最高点に達し、昼の休息が近づいたいま、マニは人々の顔にそうした問いを読み取ることができた。この国では初めについて語る術を心得た者だけが耳を傾けてもらえることを知っていた彼は、すべてがどんな風に始まったかについて語り始めた。初め、この世の成り立ちの前は、すべてが善であった。(end161)優しく芳 [かぐわ] しい風が吹き、光はあらゆる色に輝き、平穏と朗らかな節度が支配していた。そしてかの国を意のままにする神は、永遠の善き神、偉大な父、光の支配者であった。永きにわたり平安がこの天国を支配し、南方にある騒々しい小さな闇の国のことを気にかける者などいなかった。そこでは各属州の諸侯が古の昔から相争っていた。この二つの勢力はむしろ隣り合わせに併存していた。光は己のために輝き、闇は己に対し猛り狂い、それぞれが己の目的を果たしていた。ある日――それがいつのことであったか、知る者はない――闇が光に襲いかかり、闇と光、魂と物質、異質な物同士が闘いながら混じり合った。そうして第二の時代、中の時代が始まった。この世の壮大なドラマ、いま、ここ、今日、に人類は捕らわれているのだ。
マニはうねる波のような柔らかい東アラム語を話したが、彼の言葉は辛辣で、反論を許さなかった。この世のすべては、と彼はもう一度言った、善と悪、光と闇、魂と物質、二つの異なる性質のものの混合であり、それらは生と死のように、分かれてあるべきものである。したがって、この世に己の住処を求めるべきではない、家すら建ててはならぬ、子を作ることも肉を食べることも、肉欲に耽ることもならぬ。物質との接触を極力少なくするため、すべて行動は必要最低限に制限すべし。なぜなら土を耕すこと、野菜を切ること、果実を摘むこと、いや、草の茎を踏みつけることですら、その中に含まれる光の種を痛めるからだ。
(ユーディット・シャランスキー/細井直子訳『失われたいくつかの物の目録』(河出書房新社、二〇二〇年)、161~162; 「マニの七経典」)
- 一年前からニュース。
(……)新聞一面からウクライナ情勢を追う。ロシア黒海艦隊の旗艦である大型ミサイル巡洋艦「モスクワ」がおおきな被害をうけたと。新聞にはまだその情報はなかったが、同時にながれたテレビのニュースでは火災によって沈没したというロシアがわの発表がつたえられていたし、きのう時点ですでにそういうはなしはどこかでみたおぼえがある。ウクライナがわはミサイルで同艦を攻撃し、多大な損害をあたえたと主張しており、ロシアがわの報道は火災の原因についてはふれていない。米国のジェイク・サリバン大統領補佐官やジョン・カービー国防総省報道官は、攻撃を独立の事実として確認できていないが、ウクライナがわのいいぶんは妥当でもちろんありうることだと述べた。ロシアはキエフ再攻撃を示唆するようなことも言っており、東部からウクライナ軍の勢力をひきはなしたいようす。マリウポリではウクライナ兵一三四人が自発的に投降したと主張している。
日本海周辺でロシア軍の軍事演習がおこなわれてミサイルが発射されたという報もあった。欧米にくみしてロシアと対立した日本への牽制らしい。
- さらにその一年前から『浮雲』についての感想を引いている。
二時半くらいまで文を書き、一三日水曜日の記事の勤務中でいまとまっているのだが、歯磨きをするあいまに一年前の日記を読みかえしてみた。一年前の四月一五日木曜日はいろいろ引いていてながく、さいしょのほうのすこししか読んでいないが、二葉亭四迷『浮雲』についての感想がそこそこおもしろかった。さいきんもトーマス・マン『魔の山』について印象にもとづいた感想をおりおりつづったが、去年もけっこう書いていたのだなと。ライトノベルとやりくちがおなじじゃんという分析、ならびに「お勢はいまでいうところの小悪魔的な女子というのか、からかい好きな女性らしく、それに堅物の文三が焦らされ振り回されてうだうだする、みたいな調子で、だから日本の小説って一三〇年前からおなじことをやっているのか、と思った」というのはあらためて読んでみてほんとうにそうだなあというか、しょうもねえなあとおもった。すくなくとも近代をむかえて流通ということが旨となっていらい、おおくのひとにうけるやりかたというのはそう変わりはしないのだろう。
- (……)二葉亭四迷はその後も合わせていま47くらいまで読んだが、冒頭の二葉亭四迷自身の序文と、彼が相談した相手でありこの作品を世に出すにあたって寄与があったらしい坪内逍遥の推薦序文の両方とも、文章のリズム感が当然ながら現代のものとはまるで違うし、いまや失われてちっとも知らない語彙もたくさんあって、それだけでもうかなり面白い。この二つの序文はたぶん、どちらかと言うとまだ漢文の感覚をそこそこ残しているのではないか。本文も似た感じではあるのだが、いわゆる言文一致というやつで、たしかに落語家とか講談師などがいま目の前で物語を話している、というような感じを出そうとしているのが見受けられる。文体=語り口の調子自体もそうだし、ほかにもたとえば、「(……)トある横町へ曲り込んで、角から三軒目の格子戸作りの二階家へ這入る。一所に這入ッて見よう」(10)とか、「ここにチト艶 [なまめ] いた一条のお噺があるが、これを記す前に、チョッピリ孫兵衛の長女お勢の小伝を伺いましょう」(19)、「これからが肝腎要、回を改めて伺いましょう」(23)というような読者への呼びかけに、そのあたりあらわれているだろう。「回を改めて伺いましょう」というのは、この小説の区分けが「第一編」、そしてそのうちの「第~回」という言い方になっているからで、先の23の文言は第二回の締めくくりにあたるのだけれど、そういう語り口に言ってみれば紙芝居的な趣向を感じないでもない。今日はここまで、続きは次回、また聞きに来てね、という感じだ。そういう、みずからが語る物語に対して語り手が距離を取って自律しており、あれこれ言及したり評論したりしてつかの間姿をあらわすメタ的手法というのは珍しくはないのだが、二葉亭四迷のここでの紙芝居的な演出に近いものは、たとえば現代の漫画雑誌で毎話コマの外に記されているコメント、編集部なのか作者なのか主体がわからないがなんか感想じみたことを述べたり次回の内容をすこしだけ紹介したりするあれのようなかたちで残っているのではないか。それはともかく、「伺う」というのは「聞く」の謙譲語だから、話者が聞き手である読者の立場にみずから同一化しにいくような言い方で、つまり自分も話を語りながらひとりの聞き手としてみなさんと一緒に物語を聞いていますよという含みが出るので、より読者を対象化しつつ巻きこむような言葉遣いだなと思ったのだが、これは検索してみると、「《「御機嫌をうかがう」の意から》寄席などで、客に話をする。また、一般に、大ぜいの人に説明をする」という用法があることが判明した。だからやはり、語彙からしても落語や話芸のそれになっているわけだ。
- 内容としては若い男の下級官吏がやっかいになっている叔父の娘に惚れて嫁にもらおうとするのだけれど時あたかも都合悪く役所をクビになってしまってさてどうするか、というあたりまでがいまのところ。全体的に話芸の気味というか、諧謔味というか、これがいわゆる戯作、というやつの雰囲気なのか、語り手が人物をちょっと戯画化しながらユーモラスに話す感じがあって、冒頭の役所から帰る男たちの描写にすでにそれはふくまれている。二葉亭四迷はたしかツルゲーネフを読んで翻訳し、日本の文学にもあちらのやり方を取り入れようとしたとか聞いたおぼえがあるが、うだつの上がらない冴えない平役人をちょっと滑稽に扱っているあたりはたしかにロシアの、ゴーゴリなんかを思わせないでもない。ところで主人公内海文三は先に書いたとおり、叔父の娘だから従妹にあたるお勢という女性と仲良くしていて、互いに互いの好情をわかっていながらも決定的な恋愛関係もしくは夫婦関係に入る手前のぬるま湯のなかでいちゃいちゃしている、みたいなところがあるのだけれど、これライトノベルやんと思った。べつにライトノベルに限らないのだが、漫画とか大衆小説の方面とかでよくあるやつじゃん、と思って、やり口としてはかなり流通的になっている。ある夏の夜に家内がみんな出かけているなかでお勢の部屋で二人きりになるところがあるのだけれど、文三は話しているうちに自分の感情を抑えきれなくなって、もうすこしで告白しそうになるというか、ほぼもう思いを言ってしまっているような言葉を発するのだが、そこでお勢は、「アラ月が……まるで竹の中から出るようですよ、ちょっと御覧なさいヨ」(29)と出し抜けに言って風景のほうに視点を移すのだけれど、これライトノベル方面でよくあってネタにされてる、聞こえないふりをするやつじゃん、と思った。そこから記述は庭の描写に移行し、さらにお勢の姿を横からながめる文三の視線に移るのだけれど、「暫らく文三がシケジケと眺めているト、やがて凄味のある半面 [よこがお] が次第々々に此方へ捻れて……パッチリとした涼しい眼がジロリと動き出して……見とれていた眼とピッタリ出逢う」(29~30)などという動きの推移がそのあとにあって、このスローモーション的な演出も、なんと言えば良いのか、いかにも、という感じがして、ちょっと映画みたいな雰囲気もある気がするが、それで流通的なやり方になっているぞ、と思ったのだ。そのあとまた文三が思いを伝える寸前まで行きながらもひとが帰ってきてそこで打ち切りとなるのも、よく見るやつだ。こういう一夜がありつつも二人の関係はやはり決定的な踏みこみにいたらず、お勢のほうは相手が恋情に屈託しているのをどうも知りながらわからないふりをして、「アノー昨夕 [ゆうべ] は貴君どうなすったの」(31)などと言い、「やいのやいのと責め立てて、終 [つい] には「仰しゃらぬとくすぐりますヨ」とまで迫ッた」(31)りもして、実際にからだを触れ合ってもいるようで「じゃらくらが高じてどやぐやと成ッた」(32)りもしているのだけれど、こいつら何いちゃついてんねん、とまあこういう感じで、お勢はいまでいうところの小悪魔的な女子というのか、からかい好きな女性らしく、それに堅物の文三が焦らされ振り回されてうだうだする、みたいな調子で、だから日本の小説って一三〇年前からおなじことをやっているのか、と思った。まあこういうのはべつに日本に限らず、もっと昔からあるのだろうが。また、物語と人物関係としてはそんな様子だけれど、おりおり風景などの描写もけっこう仔細に書かれていて、それはわりと良い。だがこちらがいまのところ一番面白かったのは、先に触れた場面の直前、文三がお勢の部屋に招き入れられて話をしているところで、文三としてはお勢に恋しているわけだけれど、彼女とあまり仲良くしていると叔母などになんだかんだ言われ噂されるからそれは嫌で、だから彼女の部屋に入るのにも躊躇して、「お這入なさいな」(24)と言われてようやく、まだもごもごしながらも踏み入るというはっきりしないありさまで、そこでお勢は、母からはそんなに仲が良いなら結婚してしまえとからかわれる、でも私は「西洋主義」(26)で嫁に行くつもりはなし、こんなことを言ってる女は友だち連中のなかでも自分だけだし、心細いけれど、でもあなたが「親友」(27)になってくれたからよほど心強いです、みたいなことを語る。お勢はかぶれやすい気質で、隣家の娘が儒者の子で学問をものしていたのを真似て塾に行っていた時期があり、ただ肝心の学問は半端におさめたくらいで終わったようなのだが、この時点ではそこから退塾して帰ってきているわけだ。文三は「親友」関係では満足できないだろうから、あなたと「親友の交際は到底出来ない」(27)と受け、あなたは私をよくわかっていると言うが実際にはわかっていない、「私には……親より……大切な者があります……」(27)と恋情をほのめかす。それにお勢も、「親より大切な者は私にも有りますワ」(27)とこたえて、そして誰かと問われたのに断言するのが、なんと「真理」なのだ。「人じゃアないの、アノ真理」(28)と言っているのだ。ここはちょっとびっくりしたというか、唐突に出てきた大きな概念の大仰さに滑稽味をおぼえながらも、ここで、明治時代の女性に「真理」などと言わせるのか、と印象深かった。まあ、こいつ何言ってんねん、という感じではあるし、男性がこう口にしたとしても大しておどろきはなく、むしろ中二病的な臭みが出るというか、大仰さが半端に終わってわざとらしいことになる可能性が大いにあると思うのだけれど、明治時代に書かれた小説のなかで女性の人物がこう口にすると、大仰さが突き抜けて臭みとかが追いつけないところまで行っている、という感じがする。実際のところ、歴史社会を想定するに、この時期(『浮雲』第一編は一八八七年に発表されている)の女性でこんなことを言うひとはほぼまったくいなかったはずで、だから当時の読者は、いやいやこんな女現実にはおらんやろ、という受け止め方をしたのではないか。相当に奇矯な女性像として受け取られたのではないかと想像されて、そのあたりもだから、ライトノベルとか漫画とかでやたら突飛な言動をする女性キャラが、現実にはそんな風に振る舞う女性はほぼいないにもかかわらず、なぜかキャラクターとして可愛く描かれ、一定数の読者の心をつかんでいるのと似たようなことになっていたのかもしれない。作者自身も当然、こうした女性が突飛で奇矯だということは理解していたようで、だから第二回のタイトルは「風変りな恋の初峯入 上」となっているし、第三回になると「余程風変りな恋の初峯入 下」と、わざわざ「余程」をつけたして強調しているから、その点読むひとに対してことわっているわけだ。
- 外出路。
(……)三時一五分ごろに出発した。雨降り。傘をさし、バッグは提げるのではなくて左腕でかかえるようにしてあるいていく。みちのはじに薄桃色の桜の花びらが足をいざなう飾りのように点じられているがもとは知れない。雨はそこそこの降りだったはずだがひとつきくらいまえに得たような閉塞感、外界からの隔離の感覚はなく、せまく収縮した孤独の安息とはまたちがったおだやかな開放感があり、降りのわりに空気は灰に濁らずあかるめだったようだし、じつのところほとんど傘をさしていたという記憶がないくらいで、頭上を絶えず打っていたはずの雨音も耳にのこっていない。街道の工事はされていなかった。あたらしくつくられた歩道のアスファルトのうえをせっかくなので踏んでとおり、それから北側にわたって前進。濡れた路面をこすりあげて砂煙のような飛沫を撒き散らしつつ行く車の擦過音で街道はさわがしい。老人ホームの角を裏に折れて路地にはいると一軒目だか二軒目できょうも庭の端に立ったハナミズキが充実しており、アプリコットジャムをおもわせぬでもない品のよいピンクいろの花が隙なくいくつもつらなって、中心に淡緑の豆粒をひとつおきながら正面にむけてくちをひらいているそのすがたは空間に浮かんだ吸盤めいているが、雨をうけてもゆらぎみじろぎをすこしもみせずにしずかな満開を持していた。小学生とおおくすれちがった。自動車工のまえあたりまで来たところでとおくから叫びがきこえ、鳥か猫の絶叫かひとの声か断じづらかったが、じきにみちの果てから小学生の数人がつれだってあらわれたのであれだなとわかった。四、五人の男子だったが全員がまだちいさな、そろって三年生以下とみえる背丈のおさなさで、うんこしたい、ここでうんこしまーす、とか縁に草の生えたひろい空き地のまえでいいつつ前後に分かれてふらふらあるいているのにはやくもちょっと笑ってしまったのだけれど、その最後尾にならんだふたりのいっぽう、一年生にもみえるが入学直後にしては堂に入っているから二年とおもえるひょうきん者がにやにやしながらさきほどきこえた叫びを立てて、おまえだめだよ、さっきあのおばさんびっくりしてたから、と先行者を気にするひとりに制されていた。ヒヨドリが喉を張って鳴きつのっているときをおもわせる、たいした絶叫だった。中途にかかった坂を越えてふたたび細道を行くに一軒の脇にちいさな畑地でもありただの草花の場でもあるような、柿の木がなかにいっぽん立ったひかえめな挿入地があるが、その角に咲いているユキヤナギが白い房をもはや弱めて饐えた褐色をおおくさしこみつつ、雨にさからうちからもないようで横やうえに伸びながら微風にゆれるすがたを捨てて一様にみずの重さに垂れていた。
- Guardian staff and agencies, “Russia-Ukraine war at a glance: what we know on day 416 of the invasion”(2023/4/15, Sat.)(https://www.theguardian.com/world/2023/apr/15/russia-ukraine-war-at-a-glance-what-we-know-on-day-416-of-the-invasion(https://www.theguardian.com/world/2023/apr/15/russia-ukraine-war-at-a-glance-what-we-know-on-day-416-of-the-invasion))
Russian president, Vladimir Putin, has signed a bill allowing authorities to issue electronic notices to draftees and reservists amid the fighting in Ukraine, sparking fears of a new wave of mobilisation. The bill signed into law was published Friday on the official register of government documents. Russia’s military service rules previously required the in-person delivery of notices to conscripts and reservists who are called up for duty.
*
China approved the provision of lethal aid to Russia for its war in Ukraine but wanted any shipments to remain a secret, according to leaked US government documents. A top-secret intelligence summary dated 23 February states that Beijing had approved the incremental provision of weapons to Moscow, which it would disguise as civilian items, according to a report in the Washington Post. China’s foreign minister, Qin Gang, said on Friday that country would not sell weapons to parties involved in the conflict in Ukraine and would regulate the export of items with dual civilian and military use.
Ukrainian forces are finding a growing number of components from China in Russian weapons used in Ukraine, a senior adviser to Ukraine president Volodymyr Zelenskiy’s office said.
*
The 15 Russian diplomats expelled by Norway this week had sought to recruit sources, conduct so-called signal intelligence and buy advanced technology, Norwegian security police said on Friday.
*
Ukraine has barred its national sports teams from competing in Olympic, non-Olympic and Paralympic events that include competitors from Russia and Belarus, the sports ministry said. The decision published in a decree on Friday, criticised by some Ukrainian athletes, comes after the International Olympic Committee angered Kyiv by paving the way for Russian and Belarusian athletes to compete as neutrals despite Russia’s invasion of Ukraine.
- 「国と国の交渉では限界?気候変動対策を巡る変化、日本の課題は G7会合前に考える<ロングインタビュー>」(2023/4/15)(https://www.tokyo-np.co.jp/article/243776(https://www.tokyo-np.co.jp/article/243776))
日本が議長国となる先進7カ国(G7)の気候・エネルギー・環境相会合が15、16日、札幌市であり、交渉の行方が注目されている。ただ、気候変動対策を巡る国際交渉を見続けてきた専門家は「国と国の間の交渉で進めるやり方に限界が表れ始めている」とも指摘する。世界で何が起きているのか。日本に求められていることは何か。東京大大学院サステイナブル社会デザインセンターの亀山康子教授に聞いた。(デジタル編集部・福岡範行)
*
Q 亀山さんはこれまで、国の動きだけでは対策の流れを把握しきれない例として、トランプ政権下のアメリカも挙げていました。なぜでしょうか?
A アメリカの例は分かりやすいです。
アメリカが国として気候変動枠組み条約から距離を置いたのが、2回あります。京都議定書から出て行ったブッシュ政権のときと、パリ協定から撤退するんですと、当時のトランプ大統領が宣言した2017年です。両方とも(対策の枠組みに)民主党政権で合意して、選挙で共和党政権に移って、抜け出るということでした。
それが起きたときに、アメリカ国内の反応は決定的に違っていました。
ブッシュさんのときには、京都議定書はアメリカにとって経済的に悪影響を及ぼす合意であって、途上国が参加していない枠組みにアメリカが入るのはとても不公平なので、京都は失敗だし、「京都という言葉自体アメリカの国内では聞かれなくなった」というコメントも、私が2005年ぐらいにインタビューをして回ったときには聞かれました。
「Kyoto is gone(京都は終わった)」みたいな言い方をするんですよ。当時のアメリカは、そんな印象でした。
ところが、トランプさんのときには全然違っていて、抜け出ますといった翌日には「We are still in」というグループがアメリカ国内で立ち上がりました。「私たちはパリ協定に入っていますよ」という意味です。そこに州知事、市の市長、企業の社長が賛同しました。
最終的に24の州の知事が入り、企業もGoogleとかMicrosoftとかも入っていたので、アメリカという国は抜けているが、国内の主体を足し合わせると、人口やGDPの半分以上が残っているということが起こった。
似たような事象がアメリカ以外の国でも散見されています。
例えば、ダボス会議(スイスのシンクタンク「世界経済フォーラム」の年次総会)で、企業のCEOたちが集まって、気候変動が企業のリスクとしてトップに出てくる。これまでの国家間の国際交渉という、雲の上でやっているような話とは次元が違う話として、企業の方々には映ると思います。*
Q アメリカ国内の反応が違ったのは、なぜですか?
(……)
もう一つは、アメリカの中国に対するスタンスも無視できないと思っています。
京都議定書が1997年に採択されたときは中国は途上国扱いだけれども、直後から経済的に伸び始めた時期に当たっていた。議定書が発効したのは2005年。アメリカにしてみると「中国ってこれから脅威になってきそうだよね」という時代でした。「中国は安い製品をアメリカに売りつけてくるじゃないか。なぜ京都議定書は中国の排出削減目標を設定していないんだ」という意味での不公平感があったと思います。
2015年のパリ協定の後は、中国側も自分たちが世界第一の(温室効果ガス)排出量だということは自覚して、国際社会の中で批判を浴びないような立ち振る舞いをするようになってきています。下手をするとアメリカの方が悪者扱いされかねない状態になってくるんですよね。中国もある程度やるって言っているときに抜けてしまうと、アメリカだけが孤立化してしまうんじゃないかという点でも、ブッシュさんのときとトランプさんのときでは違うんじゃないと思います。
特にいまヨーロッパでは、二酸化炭素(CO2)を出して生産しているものには関税をかけようという話になってきています。対策が遅れてしまうと、アメリカの製品が売れなくなってしまったり、炭素税かけられてしまったりといった、現実的な懸念がアメリカの一部の企業にはあるんじゃないかと思います。*
Q 気候変動対策を巡る国際交渉の場は、気候変動枠組み条約の締約国会議(COP)が軸だと思います。重要性や位置付けに変化はあるのでしょうか。
A COPの重要性は下がっていなくて、年に1回、一堂に集まるのは大きいです。政府関係者だけでなくて、(企業や自治体、NGOなどの)非国家セクターの方も有名な方は集まっていて、セミナーや、タイミングを合わせた報告書の公表をしています。
2021年にイギリスのグラスゴーであったCOP26が顕著だったと思いますが、(国家間の交渉による)正式な決定文とは別に、多くのアライアンス、協力体ができました。クリーンエネルギー、自動車、金融、石炭火力をなくすようなアライアンスもありました。国だけでなく企業もいいですよ、というのも結構あり、入りたい人だけ入ってくださいと、やりたい人から始まっていく。と言いつつも、アライアンスに入っていないということが、その国に対する批判材料になり、(対策を)後押しするような影響がある。そういうものをうまく使うようになったのは、最近の国際会議の動きだと思います。
(温室効果ガスの排出を減らす)気候変動の緩和策については、まだ十分ではないけれども、ようやく非国家セクターが自発的に転がり始めたと言えると思います。*
Q 日本国内では2020年の菅義偉前首相による2050年カーボンニュートラル宣言(温室効果ガスの排出を実質ゼロにする宣言)で脱炭素化の動きが強まったと感じます。日本では国の方針に左右される部分が大きいのでしょうか。
A 国の動きに左右されるのは、全ての国が原則そうだと思います。それを前提にした上で、だけど、国内で起きている動きが、日本とヨーロッパ、アメリカとでは、かなり違う印象です。
ヨーロッパは、自国内で脱炭素への意識が高いがために国の方針につながっていると思います。
日本の場合は、菅さんのカーボンニュートラル宣言も、国内の動きで決まっている部分があります。2019年から2020年にかけては、ヨーロッパなどの国が宣言をし、自治体も宣言をして、その話が日本に輸入されて、日本の自治体が宣言をして、「じゃあ国もやって」となった。菅さんが宣言したときには先進的な企業や自治体が「やっと国が動いてくれた」と喜びました。慌てたのが、その動きに遅れをとっていた日本国内の残りの自治体と企業だと思います。
それまでは、国際条約があって、日本が合意して、国が目標を立て、自治体は国と全く同じ目標を掲げていた。上からおりてくるみたいに。
だけど気候変動対策の目標に関しては、自治体はばらばらです。例えば2030年目標をうちはもっと頑張りますとか。国とは違う設定をし始めていて、独自性が出ています。今までは見られていなかったことが日本国内で起きている気がします。*
Q 省エネで温室効果ガス排出減につながる住宅の断熱化でも、国の先を行くような目標を自治体として掲げる動きがあり、自ら先を行く例が見られる印象を受けています。
A 東京都の屋根置きの太陽光パネル(の設置義務化)もその例ですよね。
ただ、菅さんのカーボンニュートラル宣言の話に戻りますと、たしかに日本の一部の自治体と企業が(国の動きを)後押ししたんだけれども、その一部の自治体と企業は日本国民から後押しされたわけではなく、海外からの輸入なんですよね。海外のまねっこをしている。それが、今の日本の最大の問題だと思います。
2022年夏に出た国際比較の調査では、自国内の気候変動影響を心配しているかで日本は真ん中、平均的なところにいるんですけれども、国に何かをやってほしいと思う気持ちはあんまりなく、企業が気候変動に対して対処すべきかについては日本は最下位でした。
複数の世論調査で共通して見られる日本の傾向として、国民が、政府や企業が対策をとることに対して、それほど強く賛同していないと言えると思います。
使っていない部屋の電気は消しましょうとか、レジ袋は断りましょうとかは浸透しているけれども、日本人が今、やるべき一番重要なことは、自分たちが意識をもって、企業や国に対策をとることを期待していくことなんじゃないかなと思います。
- いま一〇時で、きょうはここまで籠もりきり。きのうもそうだったが。それなのでたいしたこともなし。天気は雨降りで、午前中に覚めてからしばらくはそとを行く車のタイヤ音に水気のたなびきがともなっていながらも降っているのかどうかは聞き取れず、それくらいのわずかさでたぶん降っているのだろうとおもったが、午後にはいったあたりから柵をひかえめにカンカンと打つ音が聞こえだし、降りがあきらかな気配となった。いまこの夜はまたしずまっており、止んだらしい。
- さきほど音楽を聞きながらゆっくり息でも吐くかとおもい、Brad Mehldau『Live In Marciac』を三曲聞いた。こういうときにあたらしいアルバムを聞こうとしないのがよくないところだが、まだ知らないやつはとりあえずBGM的にながしてみて、腰を据えて聞こうとおもったやつのみじっと聞きたいというあたまがある。Mehldauのこの独演は前半に三曲、クラシカルだったり現代音楽的というかやや抽象的だったりして印象にのこっているトラックがあり、それらがどういう曲なのか、どういうプレイなのかまだつかみきれていないのでひさしぶりに聞こうとおもったのだ。それで#5の"Resignation"からはじめてしまったがこれはまちがいで、#4の"Unrequited"からがくだんのちょっとつかみにくいいろあいの演奏だった。しかしもどらず、#6 "Trailer Park Ghost"と#7 "Goodbye Storyteller (for Fred Myrow)"も聞いた。いちおうこんかい聞いてこういう演奏ねというのはある程度聞き取ることができたつもりだが、しかしそうはいってもやはりわかりやすくよりどころになる色がないから、"Resignation"なんて七拍子だったことしかおぼえておらず、それいがいのことは聞いたそばからわすれている。しかし後半でしばらく速弾きするぶぶんがあったのはたしかこっちだよな? その速弾きはすごく、テクニック的にきわめてはやいという点もさりながら、ピアノをこんなふうに鳴らせるんだなというか、むしろMehldau個人の手腕よりもこんなふうに鳴ってしまえるピアノという楽器のすごさを感じるようで、こんなふうにというのはすばやくちょっともたげては沈む波打ちのぐあいだったり、高速で水平にひらいて敷かれるつらなりの粒立ちだったりでことばにしてみればよくありそうにおもえるけれど、あからさまにアウトするでもなくといってメロディックという手触りでもなく、やはり抽象的な中間色みたいな調子で、音やメロディというよりその微妙にうつりかわっていく希薄ないろとうごきとしてフレーズが聞こえるようで(つまり瞑目の脳裏に表象されるのだが)、これはと耳を寄せていた。#6のほうはまだいくぶん記憶があっていちおうテーマがあるのだけれどその旋律もなんやねんこれみたいな、バッキングがけっこうバタバタあるくみたいな感じでアブストラクトないろあいのわりにちょっと活気のある曲なのだけれど、そこに間をひろめに鷹揚に置かれていくテーマはやはり一筋縄ではいかない、あまりメロディという感じではなく、コード進行もよくわからない。しかもすぐにソロにはいって忘れ去られるし。それでいてさいごできちんともどってきたりして、いちおうこの曲はずーっとテーマの構成に沿っていろいろ展開している尋常なやりかたなのだとおもう。その展開のしかたはむろん油断ができず、乗ってくると耳を惹きつけられる。
- 煮込みうどんをひさしぶりにこしらえたのでこれから食う。
―――――
- 日記読み: 2022/4/15, Fri.
- 「ことば」: 1 - 3
2023/4/14, Fri.
禁欲のうちに修行すること、世を捨てて悪魔に立ち向かうことならだれにでもできる。神の言葉を聞いた者は多く、それを広く告げ知らせた者も少なくない。だが、天使のお告げすら、いつかは風に散る。時が吹き散らしてしまった言葉を一体だれが集め、その智慧を広めるというのか。教えはいつしか風評となり、預言者の見た未来はただの錯覚に変わる。真実となるべきものは、書き留められねばならぬ、と天使は言う。真実となるべきものは、書き留められねばならぬ、とマニは考える。ただ文字だけが、教えを正しく伝え、生きのび、その文字をとどめた素材、たとえば黒い玄武岩の塊や焼かれた粘土板、薄くのばしたパピルスの繊維やごわごわするヤシの紙と同じだけの重みを持つだろう。
(ユーディット・シャランスキー/細井直子訳『失われたいくつかの物の目録』(河出書房新社、二〇二〇年)、160; 「マニの七経典」)
- 一年前から、『魔の山』の感想。なかなかよくまとめているなという印象。書きぶりがけっこう密だ。
(……)トーマス・マン/高橋義孝訳『魔の山』の下巻(新潮文庫、一九六九年)。そろそろおわりがちかい。いま730くらいまで行った。レコード熱のあとは、エレン・ブラントというオランダ生まれのデンマーク娘が登場し、かのじょが霊媒的な体質をもっているというわけでクロコフスキーのイニシアティヴでひとびとはその研究実験に邁進し、ハンス・カストルプも部屋でおこなわれるこっくりさんに参加する。かのじょを媒介としてよびだされるホルガーという霊は詩人だといい、ひとつ詩をつくってくれとたのむとその後一時間にもわたってワイングラスは文字のうえをひたすら行き来し、長大な叙情的詩文をものするのだが、この趣向はちょっとおもしろかった。こういうオカルティックなことはいかがわしいという観念がハンス・カストルプにはあるようだし、たぶんとうじはきちんとしたおとなならこんなことに首をつっこまないという認識が広範にあったのではないか(まあ、いまでもスピリチュアル方面にはまりすぎるとやばいひとあつかいされるとおもうが)。記述の調子からなんとなくそんな印象をうける(いっぽうで一九世紀末くらいには(とくにイギリスなんかで?)交霊会が盛んにおこなわれるようになったという印象があるが、それがただしい認識なのかはわからない)。それでカストルプもいちどはこのくわだてへの参加をやめ、近代科学的合理主義を旨とするセテムブリーニ氏もとうぜんいちどめの参加を非難しつつそれに賛同しているが、しかしエレン・ブラントにやどった霊がつぎはだれであれ死者を呼びだしてみせると言ったのに誘惑され、カストルプはけっきょく実験にまた参入する。この山のうえで病死したいとこヨーアヒム・ツィームセンをみたいとおもったのだ。それで最終的にみなは実験室にあらわれたかれのすがたを目撃することになるが、「ひどくいかがわしいこと」と題されたこの一節は挿話として(断片的物語として)なかなかきれいに結構がそろえられている感触をうけた。そのつぎの「立腹病」はサナトリウム内にふしぎと好戦的な雰囲気がいきわたって、だれもかれもが激しやすくなり、喧嘩騒ぎがひんぱんにもちあがるというはなしで、反ユダヤ主義者なんかもでてきて一次大戦前という時代の空気をなんとなくおもわないでもない。この節が終わればのこるは「霹靂」という節ひとつのみである。
そのあとは『魔の山』のつづきを読みすすめて、五時まえに読了した。おもしろかった。さいしょの三〇〇ページくらいは、なにも起こらんしかといって描写に生きる作品でもないしぜんぜんすすまねえなとおもいつつその退屈さを味わっていたが、読み終わってみればたいした作品だなあという印象。さいごのひとつまえの「立腹病」の節では、732で、セテムブリーニの容態がだんだんわるくなっておりここのところは数日おきに寝込んでいるとか、それにつづいてナフタの調子もわるくなって病がすすんでいるという言及があるのだが、ここを読んだときに、形而上学的な議論をつねにはげしくたたかわせてきた永遠の論敵同士であるこのふたりもそろって病に服しているということにあるかなしかの感傷をおぼえた。そろそろかれらも死ぬのかもしれないという無常感をえたわけだが、ふりかえってみるに、この小説で死んでいくものたちはじつにあっさりと、ドラマティックな演出はほぼなしで、ひじょうに冷静な語り口のなかですみやかに死んでいく。ちかいところではメインヘール・ペーペルコルンもそうだったし、ハンス・カストルプの親しいいとこヨーアヒム・ツィームセンの死ですらが感情的な要素はほとんどなしに淡々とすぎていった。上巻の後半にもどれば、ハンス・カストルプが急にキリスト教的義侠心や死をおおいかくしてみえないものにせんとする施設の方針への反発に駆られて訪問した重症の患者たちもそうだった。国際サナトリウム「ベルクホーフ」においては病はもちろんつねにその全体にいきわたっており、死も直接ふれがたいながらもおりおりに生じてつぎなる患者によって埋められるべきいっときの不在をつくりだすのだが、そのふたつがもたらしがちな悲惨さや苦痛のいろはこの小説世界に希薄で、登場人物は基本的にだれも苦しんでいない。まったく苦しんでいないわけではなく、環境や設定からくる必然として病気への言及はむろんおおいし、はしばしで苦しげなようすやかなしみをみせるものもいないではないが、ぜんたいとしては病はここでの生活においてたんなる前提にすぎず、問い直されない前提につきものの無関心さであつかわれ、数しれぬ患者の死をみとってきたであろうベーレンス顧問官などは消失と新来の反復に馴れすぎたのか、悲愴さをおもてにしめす機会はほとんどなく、つねに軽妙な口をたたいて冗談ばかりいいつづけており、病も死も人生と運命のたわむれにすぎぬといった喜劇的達観ぶりだ。無数の患者連中においても、病気が苦悶や深刻な悲惨の相から本格的にとりあげられることはついぞなく、だれもかれもが病をむしろ誇りながらしかし同時にそれを無視するかのように山のうえでの生をそれなりに謳歌しており、語りにあらわれるそのすがたは一見したかぎりでは尋常な喜怒哀楽をたのしむ平常人のものと大差ない。なにしろみんなで夜中まで酒を飲んだり、音楽をきいたり、近間の風光を玩味しにいったり、みちならぬ男女の不倫にはしってみたり、街を散策したり、恋心にやられておもいみだしたりといったゆたかさである。そんななかでハンス・カストルプの教育者ふたりのおとろえにわずかばかりのはかなさがにじんだのは、読むこちらがかれらにつきあってきた紙幅や時間の量のせいもあろうし、また終演が間近で作品にもなんとなくニヒルないろあいがかもされてきていたからかもしれない。ニヒルといえばレオ・ナフタは上巻のカバー裏で「虚無主義者」の肩書を冠されていながらいままでその内実がいまいちわからなかったのだが、この終盤にいたってそのあたりがはっきりとえがかれていた。というのも、近代科学もひとつの信仰にすぎぬと否定したり(736~737)、絶対をみとめなかったり(742)、ヒューマニスト的リベラリズムの欺瞞をあばこうとしたり(744)しているからだ。その語り口は大仰かつ高遠でありながらも同時に「へへ、」という、ロシア古典文学をおもわせないでもない特徴的な憫笑がときにさしはさまれることでユーモアの味を一抹確保されており(743、744)、それをみるとおもわずわらってしまうのだけれど、話者は「理性の攪乱を目論んだ」(735)とか、「始末の悪いことになった」(736)とか、「陰険な底意」(739)、「悪意ある議論の実例」(739)などといっているから、一読したかぎりではセテムブリーニ氏の側についており、ナフタはこの小説において基本的には、そして最終的には否定さるべき像としてあらわれているようにみえる。訳者あとがきに紹介されていたトーマス・マンじしんの思想や政治的活動をかりに考慮にいれたり、またこの小説が設定されている一次大戦前という時代的舞台、ならびにこの小説が発表された一九二四年という時代の思潮を漠然とかんがえてみてもそれはたしかとおもえるが、ただしそう単純なはなしでもなく、レオ・ナフタの独裁的共産主義への親和やテロリズムの唱道は、一次大戦当時の欧州の別側面を憂慮とともにえがきとりつつ、またロシア革命を参照しつつ、一九二四年以後におとずれた第二次大戦の世界まで射程をのばしているようにもみえるわけだ。さらにまた、ひたすらにテロリズムにながれる極端さや、観念をただただまぜっかえして混乱させたいだけではないかという冷笑家ぶりや、ところどころ矛盾する思想の体系的瑕疵の印象はおくとしても、部分的にはかれのいいぶんは、いわゆるポストモダンの隆盛をみたのちの西暦二〇二二年になじみぶかいというか、要するにその精神の主旨は懐疑と近代批判である。それはいまや現代にめずらしいものではない。いずれにしても、健康的で明朗なる啓蒙主義者にして理性とヒューマニズムの徒であるセテムブリーニ氏がその悪逆な破壊性をゆるせるはずがなく、たびたび激論をたたかわせてきたこの二者は終盤においてついに決闘にいたるのだが、セテムブリーニが拳銃を頭上の空にむけて発砲したのを受けてナフタは武器をみずからのこめかみにむけ、ただ一息に自害して終わる。
そうしておとずれる最終節は「霹靂」という題であり、容易に予想されるとおりこの青天の霹靂とは、その後に第一次世界大戦と呼ばれるようになった戦争の勃発なのだ。それによってこの山のうえで七年をすごし、おおいに知的発展を遂げながらも病と無為をむさぼりつづけていたハンス・カストルプは、いやおうなく低地に引きもどされて一片の兵として戦争を生きることになる。この身も蓋もない歴史のちからの到来によって高山の魔境が浸食され、下界とのあいだに堅固にたもたれていた隔離がほとんど一瞬のうちに消滅するさまは、(……)さんの『双生』を如実におもいおこさせた。「彼は両脚を引寄せ、立ちあがり、あたりを見まわした。彼は魔法を解かれ、救いだされ、自由になったのを知った。――残念ながら、彼自身の力によってではなく、恥ずかしい話だが、彼一個人の解放などということはおよそ問題としないほどの、巨大な自然力のごとき外力によって、一挙に魔法の圏外へと吹き飛ばされたのであった」(780)。ハンス・カストルプが、ついにかれを「君」と親称で呼ぶようになったセテムブリーニ氏と汽車のなかから別れをかわしたあと、二行の空白がさしはさまれたのちに戦場のようすがつぎつぎと具象的に描写され、そこを前進するハンス・カストルプが大戦を生きたのか死んだのかわからないままに話者は終幕を告げる。さいごにいたって戦争の場が具体的に、詳細に描写されたことはよかった。このながながしい小説の終わりかたとしても、事前の了解どおりといえばそうだが、これいがいには終わらせようがなかったようにおもう。数日前にふれたように、この山のうえには永劫を望見させるような再帰的な時間の沈殿が支配的なてざわりをもって鎮座しており、それはこのままいつまでもつづくのだろうなという印象すらあったのだが、この永遠を終わらせるには、歴史と事件のみがもつ暴力的な切断のちからが必要だっただろう。
- ニュース。
(……)新聞一面にはバイデンがロシアのおこないをジェノサイドとはじめてみとめたという報があった。いままでは戦争犯罪だといいながらもこの語はつかっていなかったらしい。国際刑事裁判所(ICC)の調査はすでにはじまっており、フランスの法医学専門家チームもブチャにはいったという。ウクライナのイリーナ・ベネディクトワ検事総長は五六〇〇件だかの戦争犯罪を調査しており、五〇〇人いじょうの容疑者をみこんでいると発表。マリウポリ市長はCNNとのインタビューで、市民の犠牲は二万二〇〇〇人にのぼるとかんがえられると述べた。ロシア国防省はマリウポリにてウクライナ軍兵士一〇〇〇人が投降したと発表し、事実ならばさいごの拠点にいるとされる勢力の三分の一が降伏したことになるが、ウクライナ側は情報がないといって否定している。
- 「つつましく死期を占え青空にかくれた星は仇 [かたき] にならぬ」という短歌がすこしだけ良かった。
- 九時半に時刻をみて離床は一一時半。わりとだらだら。
- 雲のかかった白い空ではあるが、陽射しもあり、空気はおだやかで、ぬくもりが室内にもややこもる。
- 腕振り体操をよくやってからだをすっきりさせる。前後と左右と両方やるのがよい。
- 三時ごろ手の爪を切った。BGMにRalph Towner『At First Light』をながす。よい。diskunionのページにもう八三歳とあったとおもうが、八〇を越えてもこんなふうにギターを弾けるのだからうらやましい。
- もう食料がとぼしい。
- 食後はムージル書簡を読んだり、じきに臥位にながれて書見したり。山内昌之・細谷雄一編著『日本近現代史講義 成功と失敗の歴史に学ぶ』(中公新書、二〇一九年)。きのうなんとなく読み出したもの。105から、いま128。中国の日本にたいするイメージが悪化することになった原点としての対華二一か条要求や、一九一〇年代から三〇年代にかけての日中関係など。きのう書き抜き箇所をメモせずに読みすすめてしまい、きょうあらためてさいしょからおおざっぱに追いながらノートにメモしたが、それできのういちにちで一〇〇ページも読んでいたのかとおどろいた。しかし新書なのでそんなものだ。書き抜きメモにかんしてはティム・インゴルドの本もとちゅうからできておらず、きょうの食後にもいくらかすすめて400まで。
- ムージルは父親のしごとなかまだったという年上の友人に文学論をものしていたり、リースルというこれも詳細不明の女性にたいしてまたよくわからんことを書きおくっていたり、一九〇八年にはベルリン大学で親友になったヨハネス・フォン・アレッシュという友人にたいして博士号取得口述試験の報告をしたりしている。
- ここまでで三時半。からだがついていかないこともかんがえて業務日誌もしくは日報のような書き方にしてみようとおもってこんな感じ。これもよい。しばらくこの調子でやっていきたい。とはいうものの、それもその日そのときの体調と気まぐれしだいではあるので、ちょっとよくなっただけでまたつらつら書き出してもおかしくはない。
- 四時半ごろから買い物へ。外出中のことはのちに書く余裕があれば。帰ってくると五時台後半。しばらく横になってやすんでから食事。スーパーでひさしぶりにがっつり肉でも食いたいとおもって惣菜のロースカツを買ってきたのでそれをおかずに炊きたての米を食ったがうまいといったらない。食後は脚が疲れており立っているのがたいへんだったので、ウェブをみながら尻のうえのほうを揉んだり、両の太ももを前後ともこまかくよく揉みほぐしたり。太ももを揉むとめちゃくちゃ楽になる。汗も出てくる。いまはRalph TownerをBGMに日記を投稿しているところ。六日分から。もうだいたいいま書いてあることだけで、もし書き足すとしても日報的にちょっとだけにしてさっさとかたづけてしまおうとおもう。Ralph Townerの『At First Light』というこのソロギターアルバムはかなりよい。ちょっとすばらしい。Ralph Townerなんていままでぜんぜん注目していなかったけれど、独演をわりとよくやっているのだろうか? ほかにもソロギターアルバムがあれば聞いてみたい。
―――――
- 日記読み: 2022/4/14, Thu.
2023/4/13, Thu.
長い間女同士の行為は女と男の間の性行為を模倣している場合にのみセックスと見なされ、処罰の対象となりえた。性行為を特徴づけるのは男根 [ファルス] とされ、男根のないところにあるのは何らかの記号によって強調されることのないただの空白、見えない点、隙間、女性の生殖器と同じく埋めるべき穴にすぎなかった。
この空白につけられた息の長い表題が「トリバーデ」である。これは西暦一世紀から十九世紀までの男性によって書かれた書物に徘徊する、男の役割を演ずる女の幻影で、異様に巨大化したクリトリスもしくは男根に似た補助具の助けを借りて他の女たちと交情した。私たちが知るかぎり、自らトリバーデと名乗った女性はいまだかつていない。私たちは知っている、言葉や記号の意味は変化するものだということを。長い間、並んで記された三つの点(…)は失われたもの、未知のものを指したが、いつしか口に出されなかったこと、言葉にしえないことをも表すようになり、削られたもの、省略されたものだけでなく、未決定のものをも示すようになった。こうして三つの点は、暗示されたことを最後まで考え、欠けているものを想像するよう促す記号となった。それは言葉にしえないことや黙殺されたこと、不快なことや卑猥なこと、有罪とされることや推測的なこと、そして省略の特別な一変種として、本源的な事柄を置き換える代替物である。
また私たちは知っている、古代において省略を表す記号はアステリスクであったことを――その小(end131)さな星の印(*)が、文中のある箇所をそれに関連する欄外の注と結びつける役割を担うようになったのは中世のことである。セヴィリアのイシドールスは七世紀に著された『語源あるいは起源』の中で書いている。「星――印刷記号としての――は何かを省略した場合にその箇所に挿入される。この記号により、不在の物は明るく照らし出される」 今日この星は時として、一つの名詞になるべく多くの人とその性的アイデンティティを含ませるために使われる。省略から包含が、不在から存在が生じ、空白から豊かな意味が生まれる。
そして私たちは知っている、「レスビアーズィン」すなわち「レスボス島の女たちのようにする」という動詞が、古代において「だれかを辱める」とか「堕落させる」ことを意味する語、レスボス島の女性たちが発明したと考えられていたフェラチオという性技を表す語であったことを。ロッテルダムのエラスムスはまだその古代の格言集において、このギリシャ語をラテン語のフェラーレ、すなわち「吸う」と訳し、このようなコメントとともにこの項目を締めくくっている。「概念はまだ存在するが、こうした風習は私が思うにすでに根絶された」
そのほんの少し後の十六世紀末、ブラントームはポルノ的小説『艶婦伝』の中で述べている。「この業 [わざ] に関してレスボスのサッフォーは良い教師であったと言われる。それを発明したのはサッフォーだという説さえある。以後レスボスの女性 [レスビアン] たちは熱心に彼女を見習い、今日までそれを実践している」 その後、空白は地理的な故郷に加えて、言語的な故郷をも持つことになった。もっともアムール・レスビアンという語は近代にいたるまで、年下の男性に対する女性の叶わぬ恋を表すものであったのだが。
(ユーディット・シャランスキー/細井直子訳『失われたいくつかの物の目録』(河出書房新社、二〇二〇年)、131~132; 「サッフォーの恋愛歌」)
- 一年前からニュース。
(……)新聞一面からウクライナの報を追う。マリウポリ市長がAP通信とのインタビューで、市民の犠牲は二万人いじょうかと述べたという。通りでは遺体が絨毯のようになっているといい、ロシア軍は移動式の火葬設備で遺体を焼いているらしく、民間人殺害を隠蔽しようとしているとかんがえられると。プーチンは極東のほうで演説し、「特殊軍事作戦」の目的はウクライナ東部のロシア系住民の保護だという従来からの主張をあらためて述べ、軍事介入はやむをえない措置だったと正当化した。ちょうどテレビでもニュースでそのようすがうつされたが、欧米にそそのかされたウクライナの民族主義勢力との衝突はおそかれはやかれ起こっていたことである、欧米はロシア国民が危機のときに一致団結するつよさを理解していない、いくつかの分野では困難が生じるだろうが、われわれは乗り越え、やりとげることができる、みたいなことを言っていた。ベラルーシのアレクサンドル・ルカシェンコも同行しており、欧米の制裁にかんして協議したもよう。あと、ブチャの市民虐殺についても、シリア内戦でも化学兵器がもちいられたといわれながらのちほど真実ではないと判明した、それとおなじ「フェイク」だと、「フェイク」という語を吐き出すようにつよく発音しながら述べていた。未確認ではあるものの、マリウポリでは化学兵器がつかわれたという報告もあるらしい。アゾフ海に面する製鉄所にウクライナ軍と「アゾフ大隊」という武装組織三〇〇〇人ほどがあつまっているらしく、そこが事実上最後の拠点とみなされているらしいのだが(ロシア国防省はここから市外に脱出しようとしたウクライナ軍の「残党」五〇人を殺害したと発表している)、そのアゾフ大隊のなかに化学兵器をもちいられたと被害を訴えるひとが三人くらいいるようす。テレビでも証言者がはなす映像がながれていた。しかし米国のジョン・カービー報道官やメディアはあくまで未確認の情報だと慎重な姿勢でいる。とはいえ親露派武装組織の長はマリウポリを攻略するのに化学部隊の導入を選択肢としてあげていたらしいから、つかっていてもおかしくはない(こんかいの件にかんしては、われわれはまったく化学兵器を使用していないと否定しているが)。
(……)新聞の二面をみるとロシアはマリウポリ攻略にこだわっているという記事があり、うえにもふれた「アゾフ大隊」というのは二〇一四年のクリミア侵攻を機につくられた民族主義団体らしく、ロシアはウクライナの民族主義者らをネオナチと言って同国の「非ナチ化」を主張しているから、アゾフ大隊が本拠地としているマリウポリを征服して組織を壊滅させればおおいに名目が立つわけだ。また、プーチンは五月九日の対独戦勝記念日に勝利宣言をすることをもくろんでいるとかんがえられており、要衝マリウポリをとればおおきな戦果として国内向けにアピールもできると。
- 瞑想。
(……)風呂のなかでは瞑想じみて停まる。さいしょ窓を開けていたがそのうちに閉めると、換気扇のおとのひびきかたがかなり変わった。どこから落ちるしずくだったのか、そしてなにに落ちていたのか確認しなかったが、いっとき何個かつづいた滴音がしだいにたかさを変化させ、やや音楽的に、はっきりとした音程をもったことがあった。瞑想とはいまここの瞬間を観察しつづけそれに集中するおこないであると、たぶんだいたいどの流派であってもそういっているとおもう。それはもちろんただしいのだが、すわってじっとうごかずにいると、「いまここ」に集中していたはずがいつのまにかその「いまここ」をわすれてべつの、どこともいつともつかない「いまここ」にいる、ということがけっこうおこりうる。端的に、じぶんがいま瞑想をしている、じっとうごかずにいるということそのものをわすれて、ちょっと経ってからそのことに気づき、あ、いま瞑想してたのか、とおもいだす、ということがさいきんはある。ねむかったりして意識があまりさだかでないと夢未満のイメージ連鎖にまきこまれて現在をうしなうということがいぜんはよくあったが、それともまたちがい、意識はずっと明晰なのだ。それでいて目をあければそこにひろがっているはずの空間、そして目を閉じているあいだもきこえつづけているはずの聴覚的刺激をわすれていることがある。
- 往路。
(……)きょうはジャケットを着るとあつすぎることが目に見えていたので、ベストすがたでいくことに。今年はじめてである。荷物をととのえてうえにいき、出るまえに下着や寝間着類をたたんでソファの背に置いておいた。たたんでいるあいだ、暑さで室内の空気がちょっと息苦しいとすらかんじたが、空に薄雲がなじんでいるのでひかりを減退された西の太陽の熱が余計にこもり気味だったのかもしれない。
三時一〇分ごろ出発。そとに出れば大気にうごきのないときがなく、風は無限の舞踏と化して、こずえはふるえのつらなりとしてただおとを生む。道脇にみえる一段したの土地の、水路に接したみじかい斜面にあれはハナダイコンかあかるいむらさきの花が群れて揺れ、坂道にはいれば同様にみぎがわにひらいた空間のさきでひとつしたのみちに立った木から、かわいたみどりの葉がおもしろいようにはがれこぼれている。暑かった。坂の終盤から木がなくなって陽射しを受け取る余地がひらくが、きょうは雲にけずられて日なたのいろもかげも淡いのに、粘りをわずかはらんだような、冬の陽にないあの熱が肌に寄ってきた。杉の木の脇を街道につづくみちで、風が厚くふくらんでまえから身をつらぬきすぎていくと、ワイシャツと肌着のしたの脇腹や胸がすずしさに濡れる。五分あるいただけで汗をかく陽気だった。
きょうも道路工事はつづいているので街道と裏の交差部でとまり、交通整理員にとめられている車がなくなるまでしばらく待ってから北へわたった。整理員の服装をあらためてみると薄い黄緑色のジャンパーを着込んで手首のほうまでしっかりおおわれており、きょうの陽気ではだいぶ暑そうだし、夏場などあれではたおれるものも出るだろう、ヘルメットや蛍光テープを貼ったベストはまだしも、あのジャンパーはやめさせてやればいいのにとおもった。
街道沿いの歩道を東へ。裏に折れて自転車に乗った小学生ふたりとすれちがいながら再度折れ、路地にはいって二軒目の庭にある桃紫のモクレンはもう仕舞いだが、きょうはそのおなじ家だったかどうか、ハナミズキが咲きだしていた。まんなかにみどりの豆を乗せたピンクの、ほとんど秋の紅葉のような、紅鮭のような赤の気配をわずかはらんだ花たちが、すきまをもうけず接し合って宙を埋め、極細のかたい棒の先端にとりつけられた模型の蝶のような無数のかたちがまとめて微風にふるえている。みち沿いの家々や線路のむこうにたかまっている丘はあらためてみればけむるような若緑が冬を越えた常緑の間におおく湧いてまだらもよう、ぜんたいとしてあかるくあざやかさを増していた。風はめぐる。ある箇所でのぞいた線路むこうにひとつは日に焼けた本のページのような黄褐色を葉にふくんだ立ち木がさらさらと揺れ、もうひとつには葱色の濃いみどりの葉叢に白いものをいくつものせた木があって、ヤマボウシかとおもったがうたがわしいし、花なのかどうか眼鏡がなければよくもわからない。
(……)にあたるてまえの一軒にはサツマイモの皮をあかるく照らせたような、紅芋タルトのあれにちかいいろの花木が入り口にあり、郵便をうけとったかなにかで出ていた老人がその脇に立って背をみせており、服のうえにあるかなしかひかりとかげの交錯がうまれ、気のせいのごとくゆらいでいた。坂をわたってちょっとすすむと脇の駐車スペースに巨木がいっぽん立っていて、きのこ雲じみてもくもくとふくらむような常緑のこずえはとおるとしばしばひびきを降らせているが、このときも風におとを吐きつつ虫の産卵のように葉っぱをつぎつぎ大量に捨て、黄色く褪せた落ち葉があたりの地面に溜まったさまの、時ならずいくらか時季おくれの感があった。
- 「読みかえし2」より。
Jess DiPierro Obert in Port-au-Prince, “‘Women’s bodies weaponized’: Haiti gangs use rape in spiraling violence”(2022/11/14, Mon.)(https://www.theguardian.com/world/2022/nov/14/haiti-gangs-violence-women-rape(https://www.theguardian.com/world/2022/nov/14/haiti-gangs-violence-women-rape))
1351
It was love at first sight for Madeline, who first met Baptiste at a church retreat in Haiti’s southern port town of Aux Cayes in 2002. As infatuated teenagers, they eventually wed and settled in the Caribbean country’s capital, Port-au-Prince.
With a growing family and unsteady work selling sodas and food staples, the couple could only afford to rent in Cité Soleil, a seaside shantytown where armed groups have turned streets into battlegrounds.
The gang violence became so intense in July that Madeline and Baptiste sent their six children away to a shelter for safety. Days later, the pair awoke in the middle of the night to find the neighbourhood in flames.
Grabbing what belongings they could, they fled towards Carrefour Lanmò, or the “Crossroads of Death” – an intersection frequented by armed groups. They made it through, Madeline recalled, but an armed gang stopped them afterwards and dragged them on to a side street.
Baptiste was pushed to the ground and beaten before a tyre was thrown around his neck and he was set on fire. His last words were: “Can’t you see that we are poor?”
Madeline was raped by more than a dozen gang members. After they were done, she was told to run, forcing her to abandon Baptiste’s body.
*
Haitian women and children are not just being caught up in the country’s spiralling gang wars – they are increasingly being targeted for rapes, torture, kidnappings and killings by the 200 armed groups that now control 60% of the capital.
Their plight has been compounded by a lack of safe shelters or refuge. More than 96,000 people have been displaced by the gang violence, but neither the Haitian government nor the international community has mandated formal displacement sites – which have been set up during previous bouts of instability or disasters.
Dozens of women and girls have been raped at some of the 33 makeshift displacement camps, according to the Haiti-based Bureau des Avocats Internationaux (BAI), a legal group trying to assist some of the women who have been attacked.
*
Armed groups have proliferated since the assassination of President Jovenel Moïse in July 2021, and despite the rampant violence, a political solution has yet to materialise. Haiti’s de facto leader, Ariel Henry, has called for foreign troops to intervene, but nearly 100 civil society groups want a “Haitian-led solution” and oppose a foreign intervention.
*
With more than 60% of the population unemployed and nearly 77% living on less than $2 (£1.7) a day, much of the youth turn to gangs as a means of survival.
*
Some of the alleged abuse was at the hands of local aid workers or government officials, according to Joseph, who said neither UN agencies nor the Haitian government were taking action to address the problem.
*
Some victims and humanitarian workers said that some gang leaders use their authority to take the virginity of any young girl in their territory.
“Women’s bodies are weaponised,” said Rosy Auguste Ducena, programmes manager at the National Human Rights Network (RNDDH). “It’s a symptom of the trivialisation of rape.”
Rape was originally used as a weapon of control before Haiti gained independence in 1804, largely by colonial powers that enslaved the population and pillaged the land.
Since then, it was only recognised in Haiti as a crime after 2005, and although Moïse was set to adopt a raft of new measures that would have given women more protections – including the legalisation of abortion – no new changes can be adopted until elections.
George Monbiot, “Do we really care more about Van Gogh’s sunflowers than real ones?”(2022/10/19, Wed.)(https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/oct/19/van-gogh-sunflowers-just-stop-oil-tactics(https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/oct/19/van-gogh-sunflowers-just-stop-oil-tactics))
1357
Writing for the Mail on Sunday, the home secretary, Suella Braverman, claimed: “There is widespread agreement that we need to protect our environment, but democracies reach decisions in a civilised manner.” Oh yes? So what are the democratic means of contesting the government’s decision to award more than 100 new licences to drill for oil and gas in the North Sea? Who gave the energy secretary, Jacob Rees-Mogg, a democratic mandate to break the government’s legal commitments under the Climate Change Act by instructing his officials to extract “every cubic inch of gas”?
Who voted for the investment zones that the prime minister, Liz Truss, has decreed, which will rip down planning laws and trash protected landscapes? Or any of the major policies she has sought to impose on us, after being elected by 81,000 Conservative members – 0.12% of the UK population? By what means is the “widespread agreement” about the need for environmental protection translated into action? What is “civilised” about placing the profits of fossil fuel companies above the survival of life on Earth?
In 2018, Theresa May’s government oversaw the erection of a statue of Millicent Fawcett in Parliament Square, which holds a banner saying “Courage calls to courage everywhere”, because a century is a safe distance from which to celebrate radical action. Since then, the Conservatives have introduced viciously repressive laws to stifle the voice of courage. Between the Police, Crime, Sentencing and Courts Act that the former home secretary Priti Patel rushed through parliament, and the public order bill over which Cruella Braverman presides, the government is carefully criminalising every effective means of protest in England and Wales, leaving us with nothing but authorised processions conducted in near silence and letters to our MPs, which are universally ignored by both media and legislators.
The public order bill is the kind of legislation you might expect to see in Russia, Iran or Egypt. Illegal protest is defined by the bill as acts causing “serious disruption to two or more individuals, or to an organisation”. Given that the Police Act redefined “serious disruption” to include noise, this means, in effect, all meaningful protest.
For locking or glueing yourself to another protester, or to the railings or any other object, you can be sentenced to 51 weeks in prison – in other words, twice the maximum sentence for common assault. Sitting in the road, or obstructing fracking machinery, pipelines and other oil and gas infrastructure, airports or printing presses (Rupert says thanks) can get you a year. For digging a tunnel as part of a protest, you can be sent down for three years.
Even more sinister are the “serious disruption prevention orders” in the bill. Anyone who has taken part in a protest in England or Wales in the previous five years, whether or not they have been convicted of an offence, can be served with a two-year order forbidding them from attending further protests. Like prisoners on probation, they may be required to report to “a particular person at a particular place at ... particular times on particular days”, “to remain at a particular place for particular periods” and to submit to wearing an electronic tag. They may not associate “with particular persons”, enter “particular areas” or use the internet to encourage other people to protest. If you break these terms, you face up to 51 weeks in prison. So much for “civilised” and “democratic”.
1358
ものがなしい十一月
ものがなしい十一月だった
日ごとに空は暗くなり
風が木の葉をもぎとっていた
そのころ ぼくはドイツへ向って旅立った国境へ着いたとき ぼくは 胸が
いちだんと激しく高鳴るのをおぼえた
そればかりか おそらく目から涙が
落ちかかっていたにちがいないそして ドイツ語を耳にしたとき
ぼくは妙な気がした(end59)
心臓がほんとうに気持ちよく
血を流すとしか思えなかったちいさな琴弾きの娘がうたっていた
心をこめてうたっていた
だが調子はずれの声で それでも
娘の演奏に ぼくはとても感動した娘はうたった 恋と恋の悩みを
献身と そして再会を
苦しみがすべてなくなる
あの天上のよりよい世界での娘はうたった この世の涙の谷を
たちまち消え去るよろこびを
魂が栄光をうけ
永遠の歓喜に酔う彼岸を(end60)娘はうたった 古いあきらめの歌を
あの天国の子守唄を
民衆という大きな赤ん坊が泣きだすと
眠りこませるあの歌をその節をぼくは知っている その文句をぼくは知っている
作者の諸君もぼくは知っている
そうだ かれらはこっそり酒を飲み
おおっぴらには水を説教したのだあたらしい歌 もっとすてきな歌を
おお友よ ぼくはきみたちにつくってやろう
ぼくらはこの地上でかならず
天国をつくり出そうぼくらは地上で幸福になろう
もう飢えて悩むのをやめよう(end61)
働き者の手が獲得したものを
怠け者の腹に飽食させてはならないこの下界には すべての人の子のために
十分なパンができるのだ
ばらもミルテも美も快楽も
甘豌豆 [えんどう] もそのとおりだそうだ 莢がはじけたとたんに
甘豌豆は万人のものだ
天国なんぞは
天使や雀にまかせておこう死んでからぼくらに翼がはえるなら
天上できみたちを訪ねよう
そしてぼくらは ぼくらはいっしょに
ありがたいタートやお菓子を食べよう(end62)あたらしい歌 もっとすてきな歌
それは笛やヴァイオリンのようにひびく
贖罪歌 [ミゼレーレ] はおわり
弔鐘は沈黙する処女オイローパは婚約する
うつくしい自由の守護神と
ふたりは抱きあってよこたわり
はじめての接吻に酔うそこには坊主の祝福こそなけれ
結婚が成立したことに変りはない
花嫁 花婿 それから
ふたりの未来の子供たち万歳結婚の寿歌 [ほぎうた] がぼくの歌だ
もっとすてきな歌 あたらしい歌(end63)
ぼくの心に
最高の神聖な星があらわれる感激の星 その星の群れが燃えさかり
炎の川となってながれ散る
いま ぼくは驚くほど強くなった気がする
ぼくは樫をへし折ることができそうだドイツの土地を踏んでから
ぼくの全身に 魔の汁液が流れる
巨人はふたたび母にふれたのだ
そしてあたらしく力がわき出した(井上正蔵 [しょうぞう] 訳『ハイネ詩集』(小沢書店/世界詩人選08、一九九六年)、59~64; 「ものがなしい十一月」(Im traurigen Monat November......); 『ドイツ 冬物語』)
1359
娘が天国のよろこびを
娘が天国のよろこびを
声をふるわせて歌い 弾いているあいだに
ぼくのトランクは
プロシャの税関吏どもにしらべられた何から何までかぎまわし
シャツやズボンやハンカチまでいじりまわし
やつらはレースや宝石をさがした
それから発禁の本を馬鹿者め トランクのなかをさがすなんて
そんなところに何も見つかりはしないぞ
ぼくが旅に持って出た密輸品は
頭のなかにしまってある(end65)そこにはレース [シュピッツェ] もしまってある
ブリュッセルやメッヘルンのものより上等だ
ぼくの諷刺 [シュピッツ] の荷を解こうものなら
おまえらを突き刺し こきおろすだろう頭にぼくは宝石類をもっている
未来の王位のダイヤモンドを
あたらしい神の 偉大な未知の神の
神殿の宝物をそれに 本をたくさん頭のなかにもってきている
おまえたちに はっきり言おう
ぼくの頭は没収されたいろんな本の
さえずりさわぐ鳥の巣だ(end66)そうだ サタンの文庫にも
これより悪い本はありえない
ホフマン・フォン・ファラースレーベンの
本より危険な本ばかりだひとりの旅客がぼくのそばに立っていた
ぼくに言った プロシャの関税同盟が
偉大な税関の鎖が
いま ぼくの目のまえにある と「関税同盟は」と その男は言った
「わがドイツ国民の基礎となるでしょう
それは四分五裂の祖国を
むすびつけて一つにするでしょうそれはそとの統一をわれわれに与えます
いわゆる ものの統一を(end67)
精神上の統一は検閲が与えてくれます
真に思想上の統一はそれは内の統一をわれわれに与えます
思想や精神の統一を
外も内も統一した
統一ドイツがわれわれに必要です」(井上正蔵 [しょうぞう] 訳『ハイネ詩集』(小沢書店/世界詩人選08、一九九六年)、65~68; 「娘が天国のよろこびを」(Während die Kleine von Himmelslust......); 『ドイツ 冬物語』)
1360
この岩の上に
この岩の上にわれらは建てよう
あたらしい教会を
第三のあたらしい聖書の教会を
悩みはもう済んだわれらを長いあいだ惑わしていた
霊肉二元は亡 [ほろ] んだ
おろかしい肉体の苛責は
ついに終ってしまった聞えないのか 暗い海の神の声が
無数の声で神は話しかける(end101)
見えないのか われらの頭上の
無数にかがやく神の光が聖なる神 神は光の中にもいる
闇の中にもいる
存在するすべてが神だ
神はわれらの接吻の中にもいる(井上正蔵 [しょうぞう] 訳『ハイネ詩集』(小沢書店/世界詩人選08、一九九六年)、101~102; 「この岩の上に」(Auf diesem Felsen......); 『新詩集』)
- この日はこもって、いや通話後にスーパーに出たんだったか? わすれたが、九時から(……)さんと通話して、そのためにほんのすこしだけだがUlyssesも訳した。通話にはひさしぶりに(……)くんもちょっと顔を出して短話。
A cloud began to cover the sun slowly, wholly, shadowing the bay in deeper green. It lay beneath him, a bowl of bitter waters. Fergus’ song: I sang it alone in the house, holding down the long dark chords. Her door was open: she wanted to hear my music. Silent with awe and pity I went to her bedside. She was crying in her wretched bed. For those words, Stephen: love’s bitter mystery.
Where now?
Her secrets: old featherfans, tasselled dancecards, powdered with musk, a gaud of amber beads in her locked drawer. A birdcage hung in the sunny window of her house when she was a girl. She heard old Royce sing in the pantomime of Turko the Terrible and laughed with others when he sang:I am the boy
That can enjoy
Invisibility.Phantasmal mirth, folded away: muskperfumed.
And no more turn aside and brood.
Folded away in the memory of nature with her toys. Memories beset his brooding brain. Her glass of water from the kitchen tap when she had approached the sacrament. A cored apple, filled with brown sugar, roasting for her at the hob on a dark autumn evening. Her shapely fingernails reddened by the blood of squashed lice from the children’s shirts.
雲が太陽をゆっくりと遮りだし、やがてすっかり覆ってしまうと、陰につつまれた湾はいっそう深い緑色をたたえた。それは彼の眼下にひろがっていた、苦い体液を溜めたボウルが。ファーガスの歌。家にいるとき、ひとりで歌ったものだ、暗く尾を引く情感を抑え気味にして。寝室のドアはひらいていた。母さんが歌を聞きたがったから。畏れと哀れみとで黙りこくったぼくはベッドの横に行った。むごたらしいベッドのなかで、母さんは泣いていた。あのことばのせいなんだよ、スティーヴン、愛のもたらす苦しき神秘っていう。
いま、どこに?
母さんが隠していたもの――古ぼけた羽根扇、麝香をふりかけた房飾りつきのダンスカード、安っぽい琥珀のネックレス、鍵をかけた引出しのなかにしまってあった。子ども時代に家の日当たりのいい窓辺に吊り下げていた鳥のかご。昔、お笑い劇の『王様ターコー、おそるべし』で、ロイスが歌うのを聞いたときには、ひとと一緒になって母さんは笑った。こんな歌――おれさまったら
誰の目にも見えなくなるぜ
透明人間、お楽しみさ幻の浮かれ騒ぎ、たたまれてしまった――麝香のかおりをほのめかせて。
もう顔をそむけて思いわずらうことはない
あのがらくたといっしょに、森羅万象の記憶のなかへたたみこまれてしまったのだ。思い悩むかれの脳裏に記憶の幾片かがつきまとってくる。聖体拝領が近くなると、台所の水道から汲んでいた一杯の水。芯をくり抜いて黒砂糖を詰めたリンゴ、暗い秋の晩に暖炉の横棚に置いて焼いてあげた。子供らのシャツのシラミをつぶして、その血で赤く染まったきれいな形の爪。

―――――
- 日記読み: 2022/4/13, Wed.
- 「読みかえし2」: 1351 - 1362













